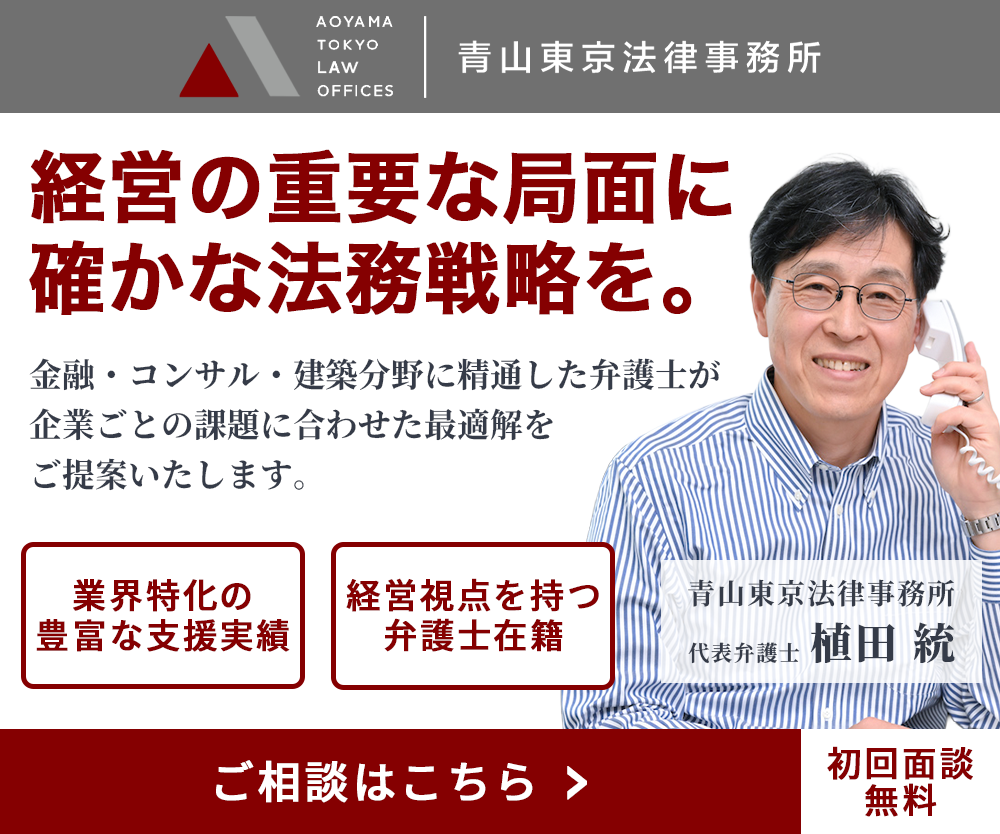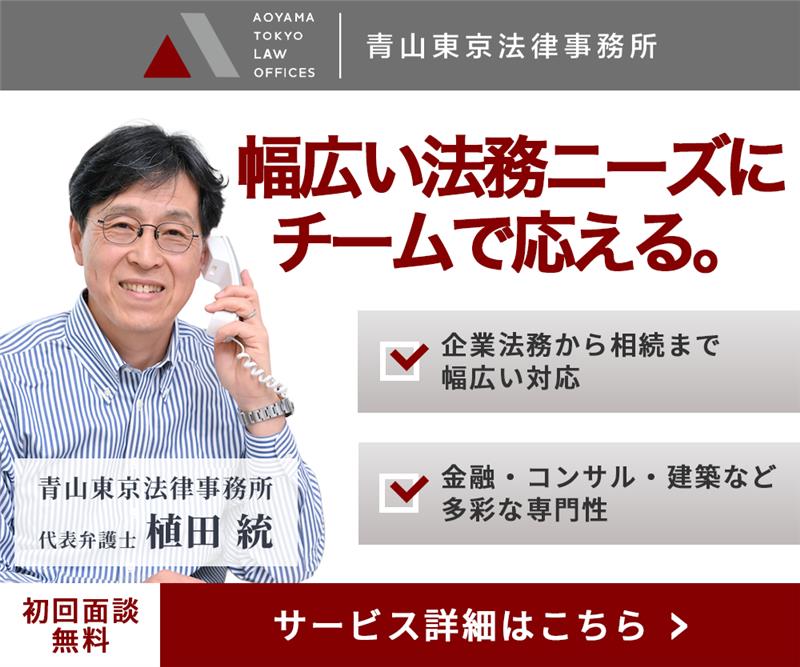公開日: 更新日:
顧問弁護士は、顧問先に対して法律に関する助言、支援などを継続的に提供する弁護士です。
会社にいない影響を心配している方もいるでしょう。
顧問契約を締結していない会社は、さまざまな法的トラブルに遭遇しやすくなります。
リスクを洗い出して対策を講じたり、法的な対応を行ったりすることができないためです。
ここでは、顧問弁護士が会社にいない場合に想定されるリスク、顧問弁護士が必要になる主な場面、顧問契約のメリットなどを紹介しています。
企業法務でお困りの方は、参考にしてください。
目次
会社に顧問弁護士は必要?

最初に結論を示すと、業種や企業規模を問わず、顧問弁護士は会社に必要といえるでしょう。
自社に適した方法で、法的リスクをコントロールしやすくなるためです。
もちろん、トラブルが起きてから弁護士を探すこともできますが、この場合は次のデメリットが生じます。
【デメリット】
- 業界の環境、会社の戦略などを理解していないため、適切なアドバイスを受けられない
- 情報収集に時間がかかるため、スピーディな対応を期待できない
- 結果的に、時間と労力がかかり報酬が高くなりやすい
また、顧問弁護士がいると、法的トラブルも未然に防ぎやすくなります。
クライアントが気づいていないリスクを洗い出して、対策を提案してくれるためです。
顧問弁護士がいないと、リスクに気づかないままビジネスを展開して、トラブルに発展する恐れがあります。
自社にとっての必要性を、慎重に検討することが大切です。
関連記事:顧問弁護士の選び方と選択を誤らないため意識したい5つのポイント
【ケース別】顧問弁護士の必要性
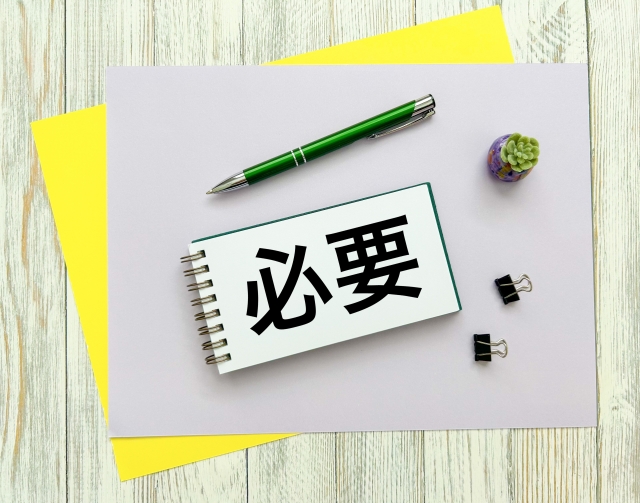
顧問弁護士の必要性は、ケースにより異なります。
ケース別の必要性を解説します。
中小企業の場合
中小企業も会社法、労働法などの適用を受けます。
また、近年は企業規模を問わずコンプライアンス(倫理および法令順守)の強化が求められています。
中小企業を経営する方の中には「うちには関係ない」という方もいますが、このような考え方は通用しません。
中小企業も関係する法律などへの対応を求められます。
近年、施行・改正された法律の例は以下のとおりです。
| 施行・改正された法律 | 主な内容 |
| 働き方改革関連法 | 時間外労働の上限規制を導入 |
| パートタイム・有期雇用労働法 | 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差を禁止 |
| 個人情報保護法 | 個人の権利、利益を害する漏洩などが発生したときに、個人情報保護委員会への報告、本人への通知を義務化 |
対応が遅れると、内部告発などで大きなトラブルに発展することも考えられます。
さまざまな法改正に、自社だけで対応することは難しいでしょう。
顧問弁護士からアドバイスを受けて体制を整えることが大切です。
関連記事:中小企業に顧問弁護士が必要な理由 | 青山東京法律事務所
業界特有の法規制が厳しい業種の場合
法規制が厳しい業界に属する企業も、顧問弁護士の必要性が高いといえます。
該当する業界の例は以下のとおりです。
【法規制が厳しい業界】
- 医療・福祉業界
- 金融業界
- 不動産業界
- 教育業界
- 放送・出版業界
たとえば、医療・福祉業界では医師法、健康保険法、薬事法、介護保険法など、金融業界では金融商品取引法、信託業法、保険業法などの理解が欠かせません。
当然ながら、これらの法律も必要に応じて改正が行われます。
日々の業務を行いながら、改正点を踏まえつつ、法的なリスクを回避することは難しいでしょう。
企業経営に注力するため、顧問弁護士が必要と考えられます。
ベンチャー企業の場合
ベンチャー企業も、顧問弁護士の必要性は高いといえます。
最先端の技術、アイデアを活用するビジネスは、法整備が追いついていないことが少なくありません。
また、業界の成長とともに、法律やガイドラインが急速に整備される傾向があります。
自社の成長だけに焦点をあてていると、急速に整備された法律などに対応できないことも考えられます。
このようなリスクを抱えているため、顧問契約を検討する必要があるのです。
ちなみに、創業間もないベンチャー企業であっても、顧問弁護士の必要性は変わりません。
法律などの急速な整備に備えて、早めに契約しておくことが大切です。
法務部門を持つ会社の場合
法務部門と顧問弁護士の役割は、原則として異なります。
法務部門の主な役割は、会社の社内に存在するというメリットを活かして、予防法務を行う、他部門のニーズに合わせて契約書の作成を迅速に行う、営業部門等と連携して自社の戦略を法務的にサポートすることです。
これに対して、顧問弁護士の主な役割は、外部の組織に属する専門家として、社内で解決できない問題について、法的な助言、支援を行うことです。
労働者との問題が紛争にまで発展してしまった場合、取引先との紛争が訴訟に発展してしまった場合等は、どうしても社内の法務部門では処理ができず、訴訟などの紛争処理の経験を有する外部の弁護士に頼らざるを得ないでしょう。
そのほかの問題についても、顧問弁護士は多くのクライアントと関わり多様な経験を積んでいるので、社内常識に縛られない客観的な視点を提供してくれます。
ですから、法務部門を持っている会社でも、顧問弁護士は必要といえるでしょう。
顧問弁護士がいない会社が抱えるリスク

顧問弁護士がいない会社は、さまざまなリスクを抱えています。
想定しておきたい主なリスクは以下のとおりです。
トラブル発生時に問題が大きくなる
顧問契約を結んでいないと、法的トラブルのリスクが高まるうえ、発生した問題が拡大しやすくなります。
主な理由は以下のとおりです。
【問題が大きくなる理由】
- トラブルの芽を発見できず初動が遅れる
- 専門家に相談できず誤った判断を下す
たとえば、残業代の支払いを求める従業員に対応せず、労働基準局から是正勧告を受ける、当該従業員から訴えられるなどが考えられます。
結果的に、企業イメージが悪化して、採用活動に支障が生じることもあるでしょう。
初動が遅れると、トラブルは拡大する傾向があります。
適切な対応を行えるように、顧問契約を締結しておくことが大切です。
契約書のリーガルチェックが不十分になる
業界に対する理解と法律の専門的な知識がなければ、契約書のリーガルチェックを適切に行えません。
顧問弁護士と契約を結んでいない場合は、この点にも十分な注意が必要です。
取引先が提示する契約書の中には、自社にとって不利な条項(取引先にとって有利な条項)を含むものがあります。
気づかずに契約を締結すると、取引を始めてから不利益が生じてしまいます。
業績などに大きな影響を与える可能性があるため、契約を締結する前にリスクや不備を洗い出して、必要があれば修正することが大切です。
顧問弁護士の多くは、顧問料の範囲内で本数を限定して簡単な契約書レビューを行っています。
顧問契約を締結しておくと、契約書にかかわるさまざまなリスクを回避しやすくなるでしょう。
労務管理に手が回らず、労使トラブルに発展する
顧問弁護士がいない会社は、労使トラブルも起こりやすくなります。
主な理由は以下のとおりです。
【労使トラブルが起こりやすい理由】
- 専門知識が不足しているため労務環境が整っていない
- 法律ではなく社内の「常識」で従業員に対応する
- 労使トラブルの対応に時間がかかる
たとえば、解雇の理由が就業規則に記載されておらず、元従業員から訴えられるなどが考えられます。
一昔前に比べると、従業員の意識は変化しています。
社内の「常識」で対応することはできません。
労使トラブルを避けるため、労務環境を整えることが大切です。
ただし、就業規則の整備、勤怠時間の管理など、やるべきことは多岐にわたります。
効率よく対処するため、顧問弁護士のサポートが不可欠です。
売掛金が回収できない
顧問弁護士の不在は、売掛金の回収にも影響を与えます。
主な影響は次のとおりです。
【主な影響】
- 初動が遅れる
- 状況に応じた必要な対応を行えない
- 取引先がまともに取り合わない
自社だけで対応すると、初動が遅れがちです。
動きはじめた頃に、取引先が倒産するケースもあります。
売掛金の回収方法は、交渉、仮差押え、訴訟など、多岐にわたります。
専門的な知識が不足していると、状況にあわせた方法を選択できません。
また、手続きに時間と労力がかかります。
自社だけで売掛金の回収を試みると、取引先が取り合ってくれないこともあります。
相手に「訴えられるかもしれない」などのプレッシャーをかけられないためです。
顧問弁護士が不在だと、売掛金を回収できないリスクが高まります。
この点も踏まえて必要性を検討することが大切です。
法改正に対応できず、法令違反として処分される
毎年のように、さまざまな法改正が行われています。
これらの中には、自社のビジネスに関わるものもあります。
専門的な知識がなければ、すべての法改正に対応することは難しいでしょう。
しかし、対応を誤ると法令違反として、処分される恐れがあります。
たとえば、時間外労働の上限を守らず、罰則が科されるなどが考えられます。
法務部門を設けていない中小企業は特に注意が必要です。
顧問弁護士と契約を結ぶなどして、最新の情報を入手できる体制を構築しておかなければなりません。
顧問弁護士のサポートが必要となる場面

顧問弁護士は、さまざまな場面でクライアントをサポートします。
以下の場面では、その必要性が特に高まります。
社員に円満退職を促すとき
業務命令に従わなかったり、ハラスメントを行ったりするモンスター社員に、退職を促したいこともあるでしょう。
従業員との話し合いで、雇用契約を終了させることは可能です(両者の合意が必要)。
ただし、退職せざるを得ない状況に追い込んだり、話し合いの過程で不適切な言動があったりすると、退職が無効と判断されて、復職を認められたり、退職する代わりに多額の和解金の支払いを命じられる恐れがあります。
このようなトラブルを防ぐため、必要になるのが顧問弁護士のサポートです。
アドバイスを受けながら、円満退職に向けて手続きを進められるため、法的なリスクを抑えられます。
新しいビジネス・新規事業を開始するとき
新規事業を開始するときも、顧問弁護士の必要性が高まります。
関連する法令、規則をチェックしてリスクを洗い出し、対策を講じておく必要があるためです。
自社で対応することもできますが、時間と手間がかかるうえ、専門的な知識がないとリスクを見逃してしまいます。
特に、業界特有の法令、規制は、わかりにくいため注意が必要です。
当該事業に精通する顧問弁護士に相談すると必要なアドバイスを受けられます。
また、リスクを評価して対策も提案してくれるでしょう。
法的手段による売掛金の回収が必要なとき
売掛金を回収できないときも、顧問弁護士のサポートが必要です。
基本的な回収の流れは以下のとおりです。
【売掛金回収の流れ】
- 請求書の発行
- 内容証明郵便による催告書の送付
- 法的手段による売掛金の回収
弁護士名義で催告書を送るだけで、売掛金を回収できるケースもあります。
法的な手段による売掛金の回収には専門的な知識が必要です。
自社だけで行うと、手続きに時間がかかってしまいます。
顧問弁護士に依頼すれば、無駄な時間を省けるうえ、取引先に妥協しない姿勢を伝えられます(売掛金の回収は原則として顧問業務外の業務です)。
顧問弁護士を積極的に活用したい場面です。
会社が顧問弁護士をつけるメリット
続いて、顧問弁護士と契約するメリットを紹介します。
メリット①予約せずにすぐに相談できる
顧問契約を締結すると、予約をしていなくても電話やメールですぐに相談できます。
多くの弁護士事務所が、顧問先への対応を優先しているためです。
気になる出来事が起きたときに速やかに相談できます。
初動が早くなるため、トラブルの拡大を防ぎやすくなるでしょう。
メリット②トラブルの早期解決が見込める
企業法務は、会社のビジネスと密接に関わっています。
単に、法律の知識があるだけでは、適切なアドバイスを行えません。
業界環境、顧問先企業の方針、取引先の傾向などを理解することで、ピントの合ったアドバイスを行えるのです。
顧問弁護士は、経営者や担当者などとの会話をとおしてこれらの情報を収集しています。
したがって、トラブルが起きたときに迅速な対応が可能です。
たとえば、事業内容、経営戦略、取引先との関係を理解しているため、契約書のレビューを速やかに行えるでしょう。
顧問契約を締結していない場合は、これらの情報を集めるところから始めなければなりません。
メリット③経営に集中できる
自社だけで、法改正に対応したり、売掛金を回収したりすることもできます。
しかし、改正のポイントや手続きを調べる作業には、多大な時間と労力がかかります。
日々の業務と並行して進めると、リソースが不足してしまうでしょう。
法律に関連する業務を顧問弁護士に任せれば、リソースに余裕が生まれるため、企業経営に集中しやすくなります。
顧問料はかかりますが、自社の生産性を引き上げられる可能性があります。
メリット④企業の信頼性が高まる
弁護士と顧問契約を締結すると、企業の信頼性も高まります。
法令を遵守している、法的リスクに備えていると捉えられるためです。
顧問弁護士がいることで、新規取引を開始しやすくなることもあります。
会社の成長にも、一定の影響を与える存在です。
ただし、単に契約しているだけでは、見込み客などにアピールできません。
コーポレートサイトに掲載しておくなどの対応が勧められます。
メリット⑤社員に安心感を与えられる
顧問弁護士がいると、従業員にも安心感を与えられます。
専門家のアドバイスを受けながら、労務環境を整えられるためです。
たとえば、最新の労働法に沿った就業規則を作成できるなどが考えられます。
会社独自のルールに縛られないため、安心感が生まれるのです。
また、整備された労務環境は、就職希望者にも魅力的に映ります。
採用活動にもプラスの影響を期待できるでしょう。
顧問弁護士の選び方
顧問弁護士を選ぶときは、以下の点に注意が必要です。
| 注意点 | 詳細 |
| 顧問弁護士の専門性 | それぞれの弁護士には専門分野がある。業界に対する理解、よく似た顧問契約の経験などを確認することが大切 |
| 顧問料と顧問契約の内容 | 顧問料、対応範囲、仕事の分量は弁護士事務所で異なる。月額顧問料の相場は5~10万円程度。これらの内容も契約前に確認が必要 |
| 顧問弁護士との相性 | 法的リスクを管理するため、さまざまな情報共有が必要になる。したがって、顧問弁護士との相性も大切。連絡の取りやすさ、レスポンスの早さもチェックしておきたいポイント |
これらの点を意識すると、納得できる顧問弁護士を見つけやすくなります。
顧問弁護士がいない会社は顧問契約を検討しましょう
ここでは、顧問弁護士がいないリスクなどについて解説しました。
主なリスクとして、契約関係や労使関係のトラブルが発生しやすく、発生後に拡大しやすい点などが挙げられます。
法務部門を設置していない会社などは特に注意が必要です。
東京の顧問弁護士・企業法務なら青山東京法律事務所は、建設業、不動産業、製造業、小売業などを対象に、40社を超える企業に対して顧問弁護士サービスを提供しています。
顧問先から上がってくる、契約書の作成・チェック、売掛債権の回収、労働問題の解決、下請業者とのトラブル収拾等、多様な問題について、豊富な経験を有しています。
顧問弁護士をお探しの方は、是非当事務所にお問い合わせください。
監修者

植田 統 弁護士(第一東京弁護士会)
東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士
東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。
野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。
米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。
2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。