
公開日: 更新日:
民事再生手続きの進め方
会社の経営が傾いてきたが、何とか再建をしたいと考えている経営者の方もいらっしゃるものと思います。その場合に選択肢となるのが、民事再生手続きです。再生計画が債権者に承認されれば、債権者から一定の債務免除を得て身を軽くし、残りの債務を分割で弁済していくことが可能になります。
実際には、こうした再建型ではなく、スポンサー企業を募ってその下で再建をしていくスポンサー型、事業を他社へ譲渡することで、会社は清算するが、事業は存続させる清算型という方法もあります。
どのように手続が進むのかを見ていきましょう。
目次
Ⅰ 民事再生手続きとは

民事再生手続きは、債務者が債権者から多数の同意を得て再生計画を定め、経済生活の再生を図るための法律的な手続きのことです。民事再生法により定められているもので、個人も法人もともに利用できる手続きです。
一般的に、民事再生手続きは会社倒産手続きの一つとして、経営陣を変更することなく破産や清算を回避し、会社の経営を立て直すために選択されます。
民事再生手続きを行うことで債務者と債権者の権利関係を調整し、会社を残しつつ債権を減らすことで、経済的な再建や事業の継続を目指せます。
関連記事:債務整理・事業再生-会社破産の費用
Ⅱ 再生計画の3つの形

民事再生法の再生計画には、以下の3つの形態があります。
(1)再建型
本業により将来的に獲得することのできる収益で債務の弁済を行い、自力で再建を図ります。
(2)スポンサー型
スポンサーからの資金援助により債務の弁済を行うと同時に、事業の再建のための資金についても支援を受けて再建を図ります。
(3)清算型
営業譲渡などを行って、営業の全部または一部を受け皿となる会社に移す一方で、旧会社は事業を移管させた後に清算を行います。この場合、旧会社は新会社に営業を譲渡した代金で債務の弁済を行います。
Ⅲ 民事再生手続きの流れ
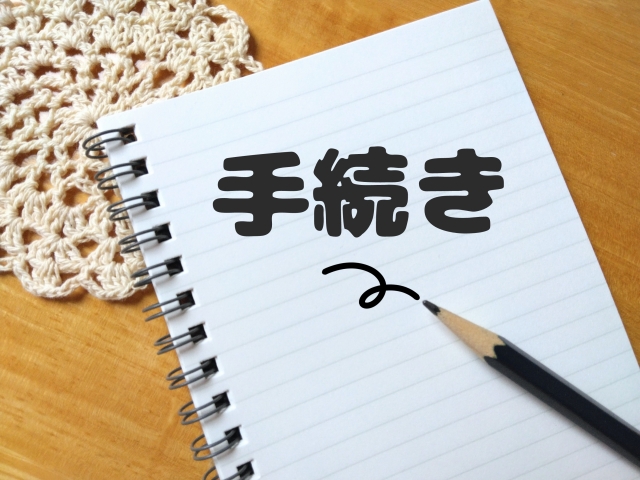
手続きは、すべて裁判所を通して行われます。
(1)申立て・保全処分
民事再生手続きをする場合は、裁判所に再生手続き開始の申立てを、保全処分の申立てとあわせて行います。保全処分とは、申立てを行った会社が、申立て前日までに発生した債務の弁済を禁止する処分のことです。
保全処分の申立てが決定すると、申立てをした会社は債務の弁済を禁止され、同時に債権者も財産の仮差押え・仮処分ができなくなります。
(2)監督委員の選任と監督命令の発令
民事再生手続きを行う場合、管財人は選任されず、財産の管理や処分は現在の会社経営者が引き続き行います。ただし、裁判所は、弁護士の中から1名あるいは複数名の監督委員を選任します。その監督委員が。会社の財産の管理・処分について同意権を持ちます。
(3)民事再生手続き開始決定
民事再生の申立てから約2週間後、正式に民事再生手続きの開始が決定されます。
しかしすべての申立てについて民事再生手続きの開始決定が下されるとは限らず、下記のような開始決定が下されない場合があります。
・民事再生手続きを行う費用の予納が行われない場合
・裁判所で破産手続きや特別清算手続きとして取り扱われており、その手続きの方が債権者の利益になると判断される場合
・再生計画の作成、再生計画の可決の見込みや再生計画の認可の見込みがないことが明らかな場合
・不当な目的で民事再生手続き開始の申立てがされた場合、あるいは民事再生開始手続きの申立てが誠実にされたものでない場合
(4)債権届出・財産評定と財産状況の報告
債権者が民事再生手続きに参加し、意思表示するために債権届出が必要です。
民事再生手続きを進める会社は、民事再生手続きの開始時点における保有財産の評定を行います。
そして、債権者から届出のあった債権(会社にとっては債務)と財産評定の結果を踏まえた財産目録・貸借対照表を作成し、財産状況を伝える報告書と一緒に裁判所に提出します。
(5)債権認否書の提出・債権調査期間
民事再生手続きを開始した会社は、債権者から提出された債権届出の内容について、認否を行うことができます。認否を行った後、民事再生を行う会社はその結果を認否書にまとめて裁判所に提出します。
(6)再生計画案の作成・決議と認可・再生計画の遂行
再生計画案は民事再生を行う会社が、その債務をどのような方法で返済していくかを計画したものです。債権者から債権届出の提出を受けた会社は、裁判所が定めた期間内に再生計画案を提出しなければなりません。そして、提出された再生計画案は、債権者集会で決議を受けます。
実際には、再生計画の中で、債権者に一定の債務免除を求め、残った債権についても分割で弁済していくことが多くなるので、それが実現可能であることを示すためにも、スポンサー企業の存在が重要です。
議決権を行使できる債権者のうち債権者集会に参加した債権者の過半数、かつ債権総額の1/2以上の賛成を得ることで再生計画案が可決されます。
再生計画案が可決されれば、裁判所はすぐに再生計画案を認可するという流れです。
再生計画が認可後、最初の3年間は監督委員監督のもと、再生計画を遂行します。
Ⅳ 民事再生手続きにかかる費用

民事再生手続きにはさまざまな費用がかかります。
必要となる費用は、民事再生手続きそのものに必要な費用と、民事再生手続き中の会社経営に必要な費用の2種類で、前者の費用としては、裁判所に納める予納金と弁護士費用があります。
(1)予納金
予納金とは、民事再生手続きをする際に選任される監督委員などの費用に充てられるものです。予納金の額は裁判所によって定められており、一律ではありません。
東京地方裁判所に民事再生を申し立てる場合の予納金の額は以下のように定められています。
| 負債総額 | 予納金基準額 |
| 5000万円未満 | 200万円 |
| 5000万円以上1億円未満 | 300万円 |
| 1億円以上5億円未満 | 400万円 |
| 5億円以上10億円未満 | 500万円 |
| 10億円以上50億円未満 | 600万円 |
| 50億円以上100億円未満 | 700万円 |
| 100億円以上250億円未満 | 900万円 |
| 250億円以上500億円未満 | 1000万円 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 1200万円 |
| 1000億円以上 | 1300万円 |
なお、予納金は申立て時に一括で納めると定められており、分割で納めることは認められませんので、必ず手元に資金を確保しておく必要があります。
(2)弁護士費用
民事再生手続きの申立て代理人となる弁護士にも報酬を支払う必要があります。その計算方法は必ずしも一定ではありません。一般的に「着手金」と「成功報酬」で報酬の額を計算しています。
着手金は裁判所に対する予納金の額と同額程度が1つの目安ですが、債務総額、債権者数が多くなると手続が煩雑になるので、報酬は高くなります。
そして民事再生手続きが完了した段階で成功報酬を支払います。成功報酬の計算方法もさまざまであるため、事前に弁護士にその金額を確認しておくべきです。
民事再生手続きを進める過程で行う債権認否・債権調査や財産評定、あるいは再生計画案の策定については、弁護士とは別に会計士や税理士などの専門家に依頼することになりますが、彼らに対しても別に報酬が必要です。
Ⅴ 民事再生手続きのメリットとデメリット
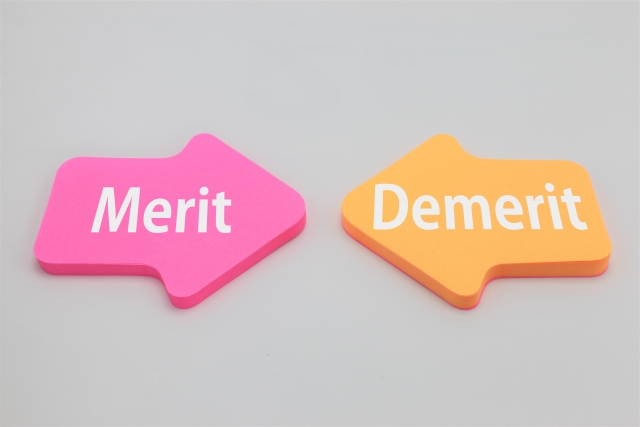
(1)メリット
民事再生手続きをするメリットとして第一に挙げられるのは、会社の事業を継続できること、つまり、それまでの事業を継続し従業員を雇用し続けることが可能となることです。
第二は、民事再生の場合はそれまでの経営陣が会社に残ることができます。引き続き事業を行おうと考えている経営者にとっては大きなメリットです。
第三は、民事再生の申立ての通知された金融機関が口座に入金された債務者の預金を相殺できなくなるため、手元資金の確保ができることです。
(2)デメリット
第一のデメリットは、会社の信用が大きく失墜することです。破産手続きとは違って会社を残すことはできますが、民事再生手続きをした会社というマイナスイメージが残ります。
第二のデメリットは、経営陣が残ることで債権者から再生計画への同意が得られず、民事再生手続きではなく破産手続きや会社更生手続きに移行することも起こり得ることです。
第三のデメリットは、民事再生手続きの場合、担保付き債権を有する債権者はその担保権を行使することが可能であることも、会社にとってはデメリットとなります。会社の財産を担保に入れている場合、その財産を差し押さえられることによってその後の再生計画が頓挫する可能性が高くなります。
第四に、債務が免除されることで、債務免除課税が発生するリスクもあります。
Ⅵ 民事再生を考えている経営者の方は是非青山東京法律事務所へご相談ください
 民事再生する会社では、債権者に債務免除を求めることになりますので、債権者の賛成が得られるような再生計画を立案できるかが勝負になります。そして、そのためにはスポンサーを見つけることができるかどうかがポイントになります。裁判所へ申し立てる前に、十分に計画を練っておくことが大切です。この準備が不十分ですと、せっかく民事再生を申し立てても、債権者の同意を得られるような再生計画がたてられず、失敗に終わってしまいます。
民事再生する会社では、債権者に債務免除を求めることになりますので、債権者の賛成が得られるような再生計画を立案できるかが勝負になります。そして、そのためにはスポンサーを見つけることができるかどうかがポイントになります。裁判所へ申し立てる前に、十分に計画を練っておくことが大切です。この準備が不十分ですと、せっかく民事再生を申し立てても、債権者の同意を得られるような再生計画がたてられず、失敗に終わってしまいます。
青山東京法律事務所では、民事再生事件を取り扱った経験がありますので、勘所を心得ています。
債務の返済が困難になり、一旦今の債務を減額してやり直したいと考えている方は、是非青山東京法律事務所へご相談下さい。
監修者

植田 統 弁護士(第一東京弁護士会)
東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士
東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。
野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。
米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。
2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。




