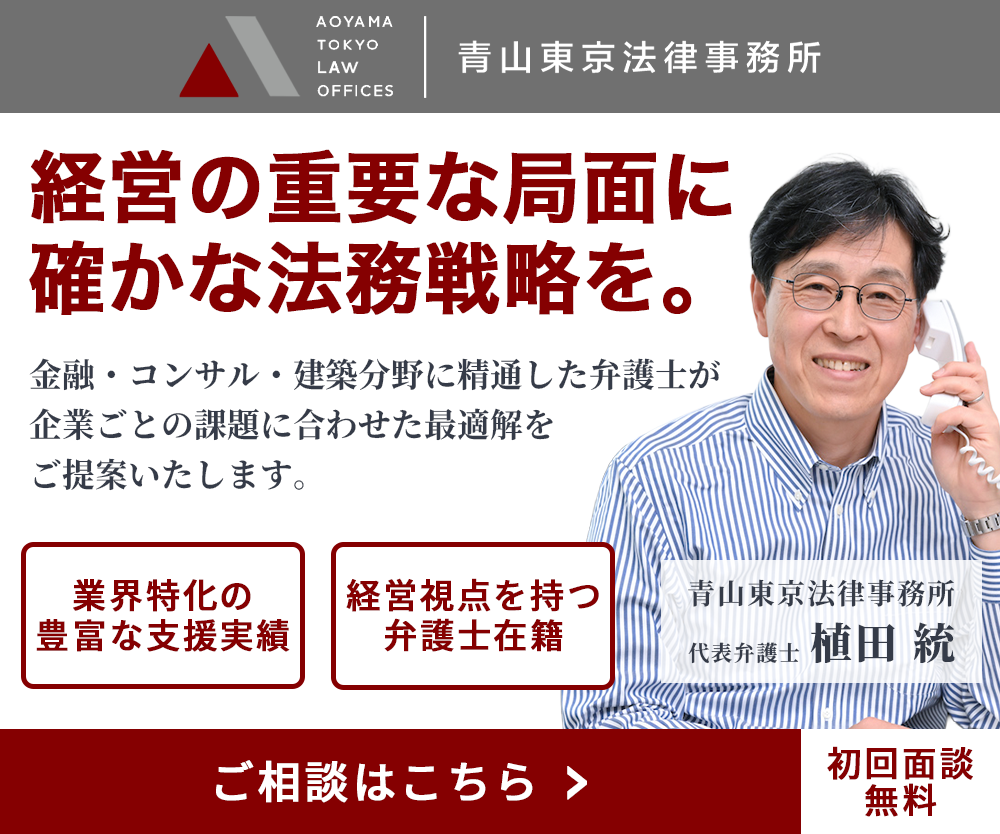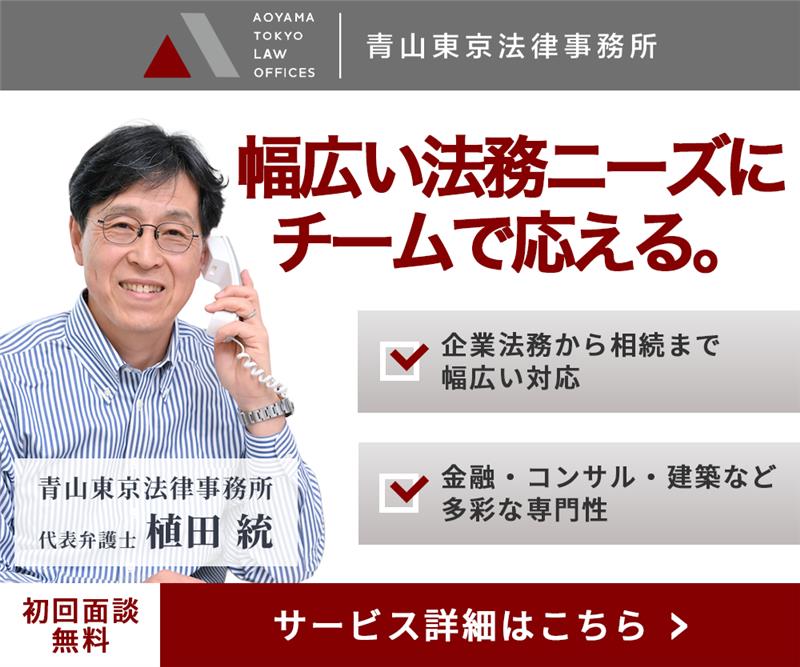公開日: 更新日:
業務上横領の典型は、社員が会社の金を使いこんでしまうという犯罪です。
ニュースを見ていると、かなり頻繁にこうした犯罪が報道されています。
一たび、社員による業務上横領についての報道がされてしまうと、会社全体が腐敗しているような印象がもたれ、会社のイメージに大きなダメージを与えます。
ここでは、業務上横領罪がどのような場合に成立するかを詳しく解説するとともに、防止策や発生した際の対応などを紹介します。
理解を深めたい方は、参考にしてください。
目次
業務上横領罪とは

刑法第253条は、業務上横領罪は「業務上自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立する犯罪といっています。
簡単に説明すると、業務の都合で預かった他人の財物を自分のものにしたり、売却したりした場合に成立する犯罪といえるでしょう。
詳しくは後述しますが、以下の要件を満たす必要があります。
【業務上横領罪の要件】
- 業務性
- 委託信任関係に基づく占有
- 他人の物であること
- 横領
具体例として、経理担当者が業務として管理していた会社の資金を私的に流用した、運送会社のドライバーが顧客から預かった荷物を無断で売却して利益を得たなどがあげられます。
出典:e-GOV法令検索「刑法(明治四十年法律第四十五号)」
単純横領罪・窃盗罪・背任罪との違い
業務上横領罪と混同しやすい犯罪として以下のものがあげられます。
| 混同しやすい犯罪 | 概要 |
| 単純横領罪 | 業務とかかわりなく、自己の占有する他人のものを横領した場合に成立する。単に、横領ということもある |
| 窃盗罪 | 他人の財物を窃取した場合に成立する。窃取は、気づかれないように盗むことを指す(刑法第235条)。「他人が占有」している財物を窃取する点がポイント。 |
| 背任罪 | 他人のために事務を行うものが、自身や第三者の利益を目的に、または本人に損害を与えるために、任務に背く行為をして財産上の損害を加えたときに成立する犯罪(刑法第247条)。 |
これらの違いを理解しておくことが大切です。
出典:e-GOV法令検索「刑法(明治四十年法律第四十五号)」
業務上横領罪の構成要件

ここでは、業務上横領罪の4要件について解説します。
①業務性
業務上横領の刑罰は、単純横領よりも重く設定されています。
業務であるからこそ他人の財物を預かる機会が生じた、また社会的な信頼を損なったと考えられるためです。
ここでいう業務は、社会生活上の地位に基づき、反復的・継続的に行われる業務や作業などを指します。
したがって、一時的な手伝いは業務性があるといえません。
一方で、給与が発生していない場合や雇用契約を結んでいない場合でも、業務性があると認められることがあります。
たとえば、自治会の会計担当者が会費を横領したケースなどは、業務性があるといえるでしょう。
一般的なイメージより幅広いケースを対象にするといえるかもしれません。
②委託信任関係に基づく占有
「委託信任関係」は、所有者から依頼されて財物を預かる関係です。
一定の信頼がベースにあるといえるでしょう。
業務上横領罪の刑罰が重い理由として、委託信任関係を破ることもあげられます。
「占有」は、事実として財物を支配している状態です。
預かった物を自由に利用したり処分したりできる状態ということもできます。
つまり、業務上横領では、単に他人の物を占有しているだけでなく、所有者から依頼を受けて占有していることが求められます。
③他人の物であること
他人の物であることも、業務上横領罪が成立する要件のひとつです。
業務上横領について定めた刑法第253条に、刑罰の対象として「業務上自己の占有する『他人の物』を横領した者」と記載されています。
ここでいう他人の物は、横領した者以外の者に所有権がある財物です。
具体例として、勤務している店舗のレジに入っている現金や顧客から預かった貴金属などがあげられます。
当然ですが、自分の所有物を処分しても業務上横領罪は成立しません。
出典:e-GOV法令検索「刑法(明治四十年法律第四十五号)」
④横領
横領は、不法領得の意思に基づく行為と説明できます。
不法領得の意思とは、他人の財物を占有している者が、委託された任務に背き、権限がないにもかかわらず、所有者にしかできない処分を行おうとする意志です。
本来であれば返却しなければならない物を、自分の所有物のように扱おうとする意思と言い換えることができます。
たとえば、経理担当者が会社の売上金を自分の口座へ移す行為、顧客から預かった荷物を転売して売上を個人的な目的に使用する行為などは、不法領得の意思に基づく(=横領)といえるでしょう。
業務上横領罪の量刑の目安
刑法第253条で、業務上横領罪の刑罰は以下のように定められています。
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
具体的な量刑は、さまざまな事情を考慮したうえで決められます。
特に重要な要素としてあげられるのが被害額です。
被害額が大きいほど量刑は重くなる傾向があります。
このほかにも、示談の成否、前科の有無なども考慮されます。
初犯であっても、罪状によっては実刑になることがあります。
業務上横領罪の時効
業務上横領罪の時効は、以下の2種類に分類されます。
【時効の種類】
- 刑事上の公訴時効
- 民事上の消滅時効
それぞれの時効について解説します。
刑事上の公訴時効
刑事上の公訴時効は、検察官が犯罪を起訴できる期間です。
公訴時効は、刑事訴訟法第250条で次のように定められています。
時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期拘禁刑に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の拘禁刑に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年
五 長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年
六 長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
つまり、業務上横領罪の公訴時効は、犯罪が終わったときから7年です(刑事訴訟法第250条)。
この期間を過ぎると、時効が完成するため検察官は横領した者を起訴できなくなります。
ただし、犯人が国外にいる場合や犯人が逃げ隠れているため起訴状の謄本を送達できなかった場合などは、時効の進行が停止します。
民事上の消滅時効
業務上横領の被害にあった場合は、加害者に対して損害賠償請求を行えます。
このときに問題になるのが、民事上の消滅時効です。
民事上の消滅時効は、所定の期間、権利を行使しないと、その権利が消滅する制度といえます。
不法行為に対する損害賠償請求権が消滅する期間については、民法第724条で以下のように定められています。
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
債務不履行(雇用契約に違反)に対する損害賠償権が消滅する期間については、民法第166条1項で以下のように定められています。
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
このように不法行為か債務不履行かで時効の期間は変わってきます。
この期間内に、損害賠償請求を行わなければなりません。
よくある業務上横領のパターン
ここからは、業務上横領のよくあるパターンを紹介します。
架空請求や経費等の不正使用
よく見られる手口のひとつに架空請求があげられます。
典型的な手口は以下のとおりです。
【典型的な手口】
- 共謀している取引先に架空の請求をして、支払われた代金の一部をキックバックとして受け取る
- 共謀している取引先に対して、割増した請求を行い、その割り増し分をキックバックとして受け取る
これらの手口は詐欺罪などに当たる可能性もあります。
経費の不正使用もよくあるパターンのひとつです。
具体的には、以下の手口などが考えられます。
【典型的な手口】
- 会社から預かった旅費を私的な旅行に費やす
- プロジェクトの経費として預かったお金を私的な娯楽に費やす
一般的に、架空請求や経費の不正使用は発覚しにくいものです。
現金の抜き取りや口座からの不正送金
現金の抜き取りもよくあるパターンといえます。
典型的な手口は以下のとおりです。
【典型的な手口】
- 集金担当者が顧客から預かったお金を抜き取り、受け取っていないと虚偽の報告をする
- 集金担当者が顧客に割り増した代金を請求して差額を抜き取る
会社の口座から経理担当者が不正に送金するケースも少なくありません。
具体的には、以下の手口などが考えられます。
【典型的な手口】
- 会社の口座から自分が管理している口座へ許可なく送金する
経理の知識を活かして、帳簿に細工をして見つからないようにしていることもあります。
経理業務が属人化している会社で起こりやすいといえるでしょう。
商品の横流しや転売
商品の横流し、転売もよくあるパターンといえます。
たとえば、以下の手口などが考えられます。
【典型的な手口】
- 営業担当者が私的なルートを使って商品を横流しする
- 倉庫作業員が商品を持ち出して買取業者に転売する
在庫管理を適切に行えていない会社で発生する傾向があります。
数量を正確に把握していないことにより、商品を持ち出しても発覚しにくいと考えられるためです。
業務上横領の防止策

業務上横領は、会社にさまざまな影響を与えます。
金銭的な被害だけでなく、ブランドイメージを失墜させることもあるでしょう。
ここでは、業務上横領の防止策を解説します。
横領の違法性を従業員に周知する
基本の対策として取り組みたいのが、従業員を対象とする法律に関する教育です。
従業員の中には、法意識が低いため罪の意識を抱かないで、漫然と業務上横領といえる行為をしてしまう人もいます。
たとえば、会社の備品を無断で持ち帰り自宅で使う、自分の楽しみのために空出張を繰り返すなどのことです。
したがって、どのような行為が業務上横領に該当するか、該当するとどのような結果になるかなどを周知することが大切です。
併せて、発覚時における会社の対応を明示することも欠かせません。
厳しく対応すると伝えることで、従業員に自制を促せます。
会社資金の管理を一人に任せない
会社の資金を2人以上で管理することも大切です。
管理を1人の役員、従業員が行っていると、業務上横領のリスクが高まります。
最近発覚した業務上横領の事例でも、1人の担当者が何年にもわたって、上司に気付かれることなく横領行為をくりかえしていたものが見られました。
2人以上の管理体制を構築し、チェック機能が働くようにしておくことが重要です。
現金を自由に引き出せない仕組みを導入する
業務上横領を防ぐため、出金の仕組みも見直しましょう。
導入を検討したいのが、現金を自由に引き出せない仕組みです。
たとえば、複数人の承認を得ないと引き出せないようにするなどが考えられます。
また、社内で保管する現金を必要最小限にすることも大切です。
身近にあるため、軽い気持ちで持ち出すことがあります。
小口現金などの管理方法も見直しておきましょう。
出金履歴をこまめにチェックする
資金の管理体制や出金の仕組みを見直しても、業務上横領を完全に防ぐことはできません。
お互いにチェックし合うはずの従業員が、結託して犯行に及ぶことも考えられるからです。
複数の対策を講じて、発見のリスクを高めておくことが大切です。
導入を検討したい対策として、出金履歴の小まめなチェックがあげられます。
たとえば、毎日、決まった時間に複数人でチェックするなどが考えられるでしょう。
このような取り組みを行うと、犯行を予防、発見しやすくなります。
手軽に取り組めるため、積極的に導入したい対策です。
定期的に内部監査を実施する
これらの対策に加えて、実施したいのが定期的な内部監査です。
上記の対策を講じても、網の目をくぐるように業務上横領を行うケースはあります。
対策を知られているため、役員や従業員による犯行を防ぎきることは難しいといえるでしょう。
内部監査で財務諸表や業務プロセスなどをチェックすれば、疑わしい行動やお金の流れを発見できる可能性があります。
また、定期的に実施することで、悪意のある役員や従業員にプレッシャーをかけられます。
業務上横領が発生した際の対応

業務上横領が発生した場合は、悪影響を拡大させないため迅速に対応することが重要です。
基本の対応は次のとおりです。
【対応の流れ】
- 資金の流れを把握する
- 関係者に事情聴取を行う
- 証拠を十分に揃える
- 横領者に対して返還を請求する
- 横領者の懲戒処分・刑事告訴などを検討する
- 会社の管理体制を見直す
これらの取り組みについて解説します。
①資金の流れを把握する
最初に、横領が疑われる資金の流れを把握します。
調査のポイントは以下のとおりです。
【調査のポイント】
- 預金口座の入出金履歴
- 横領が疑われる金額
- 横領の手口
- 関与した役員、従業員
ケースによっては、防犯カメラなどをチェックすることもあります。
さまざまな調査を実施して、事実関係を明らかにしましょう。
②関係者に事情聴取を行う
続いて、関係者から事情聴取を行います。
ここでいう関係者に、不正の疑いがある本人は原則として含みません。
本人に対する事情聴取は、証拠を揃えてから行います。
まずは、他の従業員から話を聞いて、ここまで調べた内容の裏付けを取ったり、他の従業員が行っていないことを確認したりします。
ただし、複数人で犯行に及んでいることもあります。
事情聴取の対象は、慎重に選ばなければなりません。
③証拠を十分に揃える
本人と対峙する前に、十分な証拠を集めます。
証拠が揃っていないと、犯行を認めることはほぼないためです。
また、証拠がないまま処分すると、会社が不利な立場に置かれることも考えられます。
証拠になりうるものの例は以下のとおりです。
【証拠になりうるものの例】
- 業務日報
- メール
- 請求書
- 入出金履歴
- 送金履歴
- 会計帳簿
証拠として扱えるものはケースにより異なります。
弁護士と相談しつつ慎重に対応することが重要です。
証拠がない場合も、弁護士に相談すると別の角度から新たな証拠を見つけてくれることがあります。
関連記事:会社に顧問弁護士は必要?主な役割・メリットと費用相場を確認
④本人に対する事情聴取を行う
十分な証拠が揃ったら、本人に対する事情聴取を実施します。
事情聴取のポイントは以下のとおりです。
【事情聴取のポイント】
- 相手の話をしっかり聞く
- 証拠をもとに矛盾点を指摘する
- 「いつ」「どこで」「なにをしたか」を明らかにする
- 共犯者の有無を確認する
- 双方の発言を記録する
本人が犯行を認めた場合は、横領した資金の返済を求めます。
返済請求の主な方法は次の2つです。
【返済請求】
- 返済交渉(話し合い)
- 民事訴訟
民事訴訟は負担が大きいため、話し合いで返済を求めることが一般的です。
合意に達した場合は、横領者が署名押印をした債務返済契約書などを作成します。
本人が横領を認めないときは、弁明書の提出を求めるとよいでしょう。
⑤横領者の懲戒処分・刑事告訴などを検討する
次に、横領者に対する会社の対応を検討します。
就業規則に違反しているうえ、会社の秩序も乱しているため、懲戒処分の対象になると考えられます。
金銭の多寡にかかわらず、最も重い懲戒解雇を認められる可能性が高いでしょう。
会社の信頼を裏切り、重大な規律違反を犯しているためです。
ただし、懲戒権の乱用に気をつける必要があります。
十分な証拠を集めるとともに、弁護士などの専門家と処分内容を慎重に検討することが大切です。
刑事告訴の必要性も考える必要があります。
業務上横領は親告罪ではありませんが、社内で発生するため告訴しなければ捜査が始まることも社外へ知られることもほとんどありません。
さまざまな影響が考えられるため、メリットとデメリットを理解してから適切な判断を下しましょう。
関連記事:犯罪を犯した社員は解雇できる?注意点や手続きを解説
⑥会社資金の管理体制を見直す
最後に、管理体制の見直しを行います。
防止策に何かしらの不備があったと考えられるためです。
犯行手口を確認して、同じ問題が発生しないように新たな対策を講じます。
抜け穴をひとつずつ塞いでいくことが大切です。
業務上横領の構成要件を理解して対処
ここでは、業務上横領の構成要件、量刑の目安、防止策などについて解説しました。
業務上横領は、4つの要件を満たすと成立します。
詳細を理解して対応することが大切です。
ただし、実際の対応では、法的な専門知識を求められます。
必要に応じて、弁護士に相談することも検討しましょう。
東京の顧問弁護士・企業法務なら青山東京法律事務所は、中堅・中小企業と多くの顧問契約を結んでいますが、時折会社資金の使い込みについて相談を受けることがあります。証拠の収集から始まり、本人へのヒアリング、その従業員の処分と一連の手続をサポートしています。従業員の処分については、額が小さければ返金と退職勧奨、額が大きければ、刑事告訴と懲戒解雇を検討することが通例となっています。
業務上横領等、役員、従業員の不正行為を発見した時は、是非青山東京法律事務所へお問い合わせください。きっと、お役に立てるものと思います。
監修者

植田 統 弁護士(第一東京弁護士会)
東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士
東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。
野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。
米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。
2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。