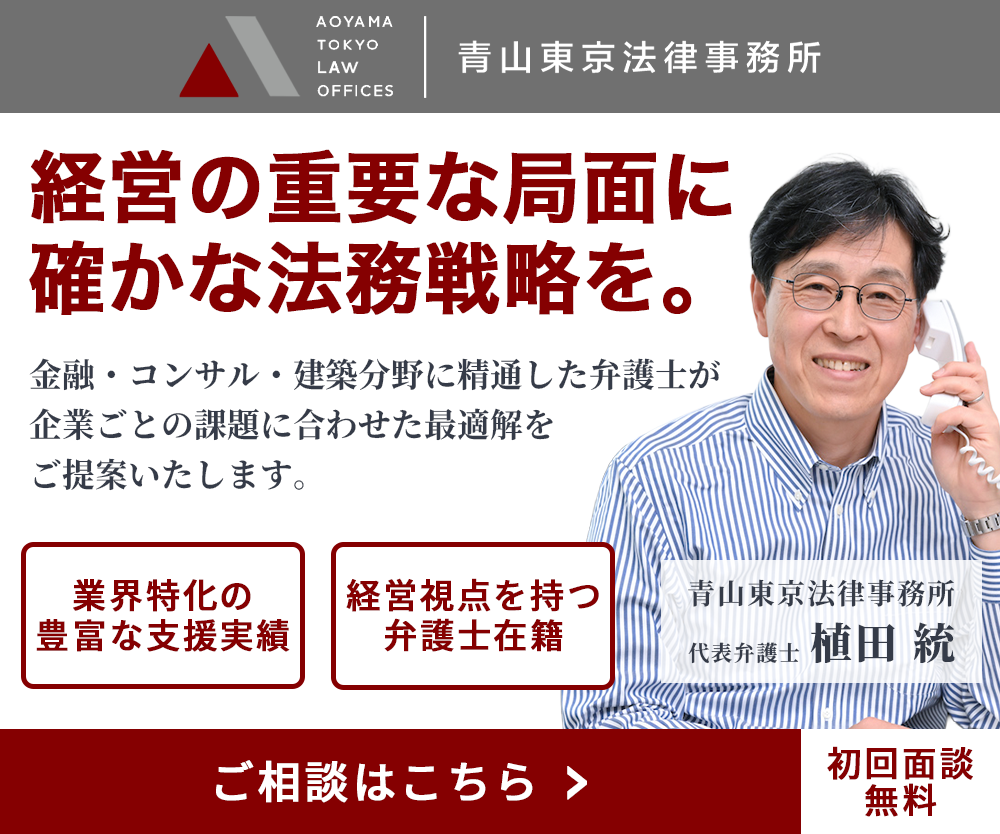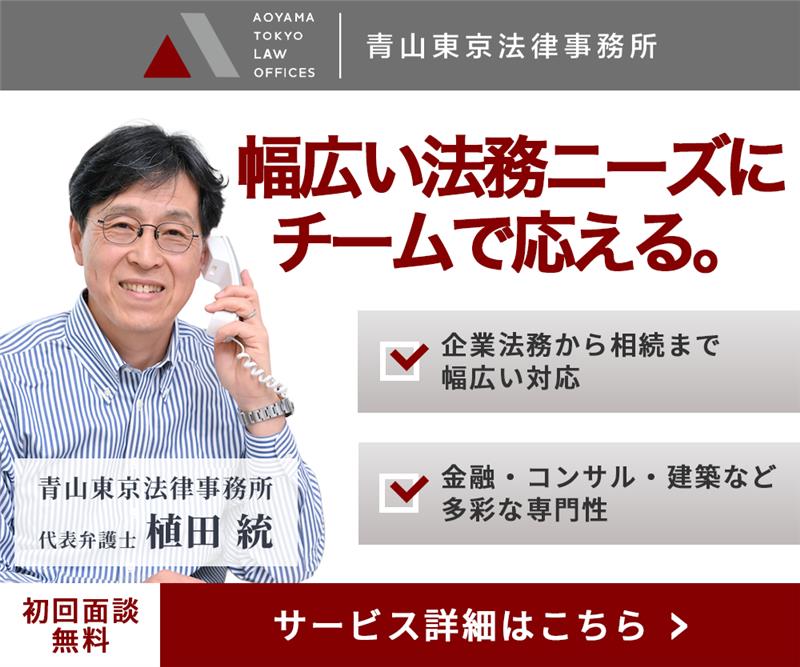公開日: 更新日:
顧問弁護士は、クライアント企業の経営戦略の実行を法務面から支える法律の専門家です。
一人の顧問弁護士ですべてが足りればいいのですが、企業の中には複数の弁護士と顧問契約を結んでいるところがあります。
ここでは、複数の顧問弁護士がいるメリット、デメリット、複数の顧問弁護士を活用したいケース、実際に依頼するときに注意したいポイントなどを解説しています。
導入を検討している方は参考にしてください。
目次
顧問弁護士とは

顧問弁護士は、契約を締結したクライアント企業から企業活動に関係する相談を日常的に受けて、必要なアドバイスやサポートを行う弁護士です。
法的なリスクを回避したり、トラブルの芽を早期に摘んだり、発生したトラブルを解決に導いたりして、クライアント企業の利益を守ります。
具体的な相談内容はさまざまです。
参考に、よくある相談内容を紹介します。
【相談内容の例】
- 労働問題
- 取引先とのトラブル
- 契約書レビュー
たとえば、就業規則について相談する、取引先から提案された契約書のリスクを確認するなどが考えられます。
顧問料の目安は、月額5~10万円程度です。
この金額内で受けられるサービスはケースで異なります。
一般的なサービス内容は以下のとおりです。
【サービスの例】
- 顧問弁護士表示
- 契約書レビュー
- 電話、メールによる相談
原則として、執務時間や各サービスの利用回数は制限されています。
顧問契約を結ぶ主なメリットは以下のとおりです。
| メリット | 概要 |
| 自社のビジネスにあわせたアドバイスを受けられる | 経営戦略、事業内容、取引先などを理解しているため、オーダーメイドのアドバイスを受けられる |
| 速やかに対応してくれる | クライアント企業を他の案件より優先してくれる |
| コストを抑えやすい | 自社のビジネスを理解しているため、情報収集に時間がかからず、コストを抑えやすい |
企業の中には、複数の顧問弁護士と契約しているところがあります。
どのようなメリットを期待できるのでしょうか。
関連記事:顧問弁護士の選び方と選択を誤らないため意識したい5つのポイント
顧問弁護士を複数依頼するメリット

複数の法律事務所に、顧問弁護士を依頼する企業が増えています。
期待できるメリットが大きいからといえるでしょう。
想定される主なメリットは以下のとおりです。
関連記事:顧問弁護士を雇うメリットと契約締結前に確認したい5つのポイント
メリット①慎重な意思決定ができる
顧問弁護士が複数いると、意思決定の質を高めやすくなります。
得意分野や経験が異なる顧問弁護士からアドバイスを受けられるためです。
それぞれの意見を比較、検討してから意思決定を行えます。
もちろん、1人でも意思決定の質は高められますが、複数人体制に比べると以下の問題が生じやすくなります。
【気をつけたい問題点】
- 相談内容によって、弁護士による得意、不得意がある
- 微妙な法律問題の場合、弁護士によって意見が異なる
- その背景には、各弁護士の経験の違いがある
複数人で対応すると、カバーできる範囲が広くなるうえ、意見の偏りも防げます。
それぞれから率直な意見を引き出しやすくなる点もポイントです。
意思決定の精度を高めたい場合は、複数人体制の導入が有効です。
メリット②それぞれの分野に強い弁護士に相談できる
それぞれの弁護士には得意分野があります。
企業法務、公益活動、民事事件、刑事事件など、幅広い範囲を扱うためです。
たとえば、企業法務だけでも以下の分野などにわかれます。
【企業法務の分野】
- 労務
- 契約
- 債権回収
- 会社法
- 知的財産
- 法令遵守
- M&A、事業継承
- 紛争解決
それぞれの分野が、さまざまな法律と関わりをもっています。
労務分野であれば、労働基準法、労働契約法、労働組合法などがあげられます。
幅広い範囲を扱うため、それぞれの弁護士に得意分野があるのです。
得意分野が異なる複数の顧問弁護士がいると、相談内容に適したアドバイスを受けやすくなります。
したがって、トラブルの予防や早期解決を目指せます。
以上のメリットを意識して、複数の顧問契約を結ぶ企業が増えているのです。
メリット③複数のトラブルに対して迅速な対応が見込める
企業活動を行っていると、複数のトラブルが同時に発生することもあります。
たとえば、取引先A社と契約内容を調整しているときに、従業員からパワハラの訴えがあるなどが考えられます。
顧問弁護士は基本的にクライアント企業を他の案件より優先しますが、キャパシティを超えるほど依頼が集中すると対応が遅くなります。
とはいえ、クライアント企業からすると、状況を悪化させないため、今すぐ対応してほしいこともあるでしょう。
複数人体制を構築していると、トラブルごとに相談先をわけられるため、迅速な対応を期待できます。
前述の例であれば、契約内容の調整は商取引に強いB弁護士、パワハラの訴えは労務問題に強いC弁護士に相談するなどが考えられます。
初動が早くなるため、状況の悪化を防げる点もポイントです。
メリット④総合的なコスト削減につながる
当然ですが、複数の顧問契約を結ぶと、原則としてその数だけ顧問料がかかります。
一見すると割高に思えますが、自社で法務部を立ち上げるより人件費を抑えられます。
アドバイスの質も、社内弁護士より、その分野で専門性の高い顧問弁護士からのものの方が高いものです。
【コストを抑えられる理由】
- 弁護士の得意分野を考えて相談できる
- それぞれの弁護士が自社の経営方針、問題点などを理解している
- 相談回数を増やせる
時間をかけずに相談を行えるため、結果的にコストを削減できるのです。
また、複数の顧問契約を結ぶことで相談回数も増やせます。
法的リスクを回避しやすくなるため、想定外のトラブルによる損失の発生も防ぎやすくなるでしょう。
ちなみに、法律事務所によっては、着手金割引などのサービスも受けられます。
メリット⑤本社と距離が離れた支店でもすぐに相談できる
本社とは別に支店を構えている場合は、拠点ごとに顧問弁護士と契約を結ぶこともできます。
期待できるメリットは以下のとおりです。
【メリット】
- 改めて情報収集を行う必要がない
- 移動の時間がかからない
- 地域の事情に精通した顧問弁護士に相談できる
支店の担当者から日常的に相談を受けているため、最低限の情報収集でアドバイスやサポートを行えます。
本社のあるエリアから支店のあるエリアまで移動する必要もありません。
したがって、トラブルが起きたときに、すぐに対応できます。
拠点単位で体制を整備しておくと、よりきめ細やかなサポートを見込めます。
顧問弁護士を複数依頼するデメリット

複数人体制にはデメリットもあります。
基本的なポイントは以下のとおりです。
デメリット①弁護士間の見解が分かれると判断に迷う
複数の顧問弁護士がいると、企業の意思決定が難しくなることもあります。
同じ案件であっても、見解が分かれることがあるためです。
見解がわかれる主な理由として以下の点があげられます。
【主な理由】
- 法律の解釈に幅がある
- 重視するポイントが異なる
- 経験や得意分野が異なる
安全を優先する弁護士と実務の都合を優先する弁護士で、意見がわかれることも考えられます。
簡単に、白と黒の区別をつけられる案件はそれほど多くありません。
見解がわかれたときに、最終的な意思決定を行うのはクライアント企業の経営陣です。
自社の判断基準を明確にしたうえで、案件の全体像を把握し、それぞれの見解を比較・検討することが重要といえるでしょう。
デメリット②コストがかさむ可能性がある
多くの法律事務所は、顧問契約に月額料金制を採用しています。
料金の目安は、1名あたり5~10万円/月程度です。
以上の仕組みを前提とすると、契約数とともにコストは増加します。
たとえば、月額5万円であれば、2名と契約すると10万円/月、3名と契約すると15万円/月かかります。
これらに加え、追加費用がかかりやすい点もポイントです。
顧問料に含まれない業務を依頼すると、原則として報酬が発生します。
したがって、相談したい分野や内容を踏まえて、必要性を検討することが大切です。
「メリット④」で説明したとおり、適切に活用できれば結果的にコストを削減できることもあります。
負担額が気になる場合は、自社に適した活用方法を検討してから依頼しましょう。
顧問弁護士の複数依頼を検討すべきケース

続いて、複数の顧問弁護士へ依頼したいケースを紹介します。
現在の顧問弁護士の対応に不満を感じたとき
顧問弁護士の対応に不満がある場合は、複数契約を検討してください。
具体例として以下のケースがあげられます。
【不満を感じるケース】
- 対応が遅い
- コミュニケーションをうまくとれない
今の時代に対応していない、昔気質の弁護士のいる法律事務所は、対応が遅くなる傾向があります。
相談内容によっては、時間経過とともに選択肢が狭まり、状況がさらに悪化し得るため注意が必要です。
複数の相談先を持つことで、このようなトラブルを未然に防げます。
顧問弁護士と効果的なコミュニケーションをとれないこともあります。
質問の意図が伝わらない、曖昧なアドバイスしか受けられないなどが考えられます。
すぐに解約できればよいのですが、先代社長の時代から付き合いがあるなどの理由で解約できないこともあるでしょう。
別の相談先があれば、良好なコミュニケーションを図って適切なアドバイスを受けられます。
現在の顧問弁護士が得意な分野以外のトラブルが発生したとき
各弁護士の得意分野、苦手分野は異なります。
労務関連は得意だがIT関連は苦手、会社法関連は得意だが海外関連は苦手などが考えられます。
得意分野外の相談が必要になった際も、別の顧問弁護士への依頼を検討すべきです。
専門的な知識・経験が不足していると、回答に時間がかかったり、一般的なアドバイスしか受けられなかったりする恐れがあります。
法的リスクを十分に回避できないことも考えられます。
事業規模の拡大に応じて、基本的に相談内容の幅は広くなります。
顧問弁護士1人で対応できなくなった場合は、複数人体制を構築するとよいでしょう。
各弁護士の得意分野は、公式サイトに掲載されている実績などを参考にすると把握できます。
自社と顧問弁護士の方向性や方針が異なるとき
原則として、顧問弁護士はクライアント企業の方向性や方針を尊重してくれます。
しかし、常に考えが一致するわけではありません。
ときには、クライアント企業の方向性、方針から外れたアドバイスをすることもあります。
たとえば、クライアント企業はスピード感、顧問弁護士は安全性を重視するためブレーキをかけるという場合です。
顧問弁護士の意見を尊重すると、自社の望む形でビジネスを展開できません。
一方で、アドバイスを無視すると不安が募るでしょう。
このようなケースも、複数の依頼が勧められます。
クライアント企業としては、スピード感をもって経営を進められるように、そのリスクを最小化するような提案をしてくれる弁護士を探したいものです。
社内で担当弁護士を使い分けたいとき
企業活動を行っていると、事業や業務にあわせたアドバイスを受けたいと感じることがあります。
このようなときも、複数の顧問弁護士と契約を結びたいタイミングです。
既に何かしらの不満を感じているため、1人体制ではニーズを満たせないと考えられます。
たとえば、労務関係は満足しているが、契約関係は満足できないなどが考えられるでしょう。
複数の顧問弁護士がいると、それぞれの得意分野にあわせた相談を行えるため、アドバイスの質を高められます。
また、分野ごとの担当が明らかになることで、これまでより相談を行いやすくなります。
問題の早期発見、早期解決にも効果的です。
顧問弁護士を複数依頼した事例
近年、コンプライアンス重視や事業ごとの専門性の高まりを背景に、複数の顧問弁護士と契約する企業が増えています。
ここでは、これらの企業の中から成功例を紹介します。
分野ごとに強みのある弁護士を利用した事例
長年にわたり食品の製造業を営んできたA社。
製造業に強い顧問弁護士から、充実したサポートを受けていました。
大きな変化が訪れたのは2年前です。
経営不振に陥っていたグループ会社の不動産事業を引き継ぐことになりました。
顧問弁護士に相談したところ、不動産事業には別の規制知識が必要と指摘され、不動産業界に詳しい弁護士と契約しました。
現在は、新しい顧問弁護士から業界特有の法的リスクに関するアドバイスを受けられています。
弁護士を使い分けたことで、大きなトラブルに遭遇することなく不動産事業を続けられているとA社の経営者は考えています。
セカンドオピニオンのために複数依頼した事例
イベント開催に向けて、設備関係の工事を依頼したB社。
しかし、工事は間に合わず、B社はイベント開催を行うことができなくなりました。
B社は補償を求めて、顧問弁護士を介して、設備会社と交渉を行いましたが解決には至らず、調停へと進むことになりました。
顧問弁護士が同様の案件を経験したことがなかったため、B社は別の弁護士と顧問契約を結びセカンドオピニオンを求めることにしました。
新しい顧問弁護士は、B社から提供を受けた資料を見て、設備会社の工事の問題点をすぐに把握してくれました。
その結果、希望額には及ばないものの、納得できるだけの補償を得られました。
リスク管理を目的に別の弁護士と顧問契約した事例
地方で小売業を展開するC社の社長は、ある顧客からC社が販売した商品に欠陥があった、金を払わないとSNSで商品の欠陥をばらすぞと脅され金銭を要求されました。
顧問弁護士に相談しましたが、この顧客と対峙して交渉することに足がすくんでしまい、何も対応してくれません。
事業に与える悪影響を心配した社長は、刑事事件にも強い弁護士と顧問契約を締結して対応を依頼しました。
毅然とした態度で妥協のない交渉をしてくれたことから、この顧客は告訴されることを免れるため、金銭の要求をあきらめた上に、謝罪文を提出してきました。
その後も、万が一のトラブルに備えて、新しい弁護士と顧問契約を継続しています。
顧問弁護士を複数依頼する際の注意点
ここからは、複数の顧問弁護士に依頼する際に気をつけたいポイントを解説します。
セカンドオピニオンを実施する際は、同じ情報を提示する
セカンドオピニオンを求める場合は、同じ情報を提示することが重要です。
別の情報を提示すると、前提条件が変わってしまいます。
意図せず提示する情報を調整して、アドバイスの内容を誘導してしまうことがあります。そうなると、異なる意見が得られても、参考にできないことになります。
意思決定の質を高めたい場合は、同じ情報を提示して客観的な意見を求めることが大切です。
自社に適した料金プランを選択する
複数人体制を構築する際に、問題になりやすいのが顧問料です。
人数が増えると、顧問料の合計金額も増えてしまいます。
対策として取り組みたいのが、自社に適した料金プランの選択です。
多くの法律事務所は、複数の料金プランを用意しています。
金額で執務時間、業務内容に差をつけていることが一般的です。
したがって、想定される利用方法に応じてプランを選べば、顧問料を節約できる可能性があります。
たとえば、専門的なアドバイスのみを求めている場合は、ミニマムな料金プランでも問題ないでしょう。
弁護士に複数依頼していることを伝える必要はない
人間関係を気にして、新しい弁護士と顧問契約を結びにくいと感じている方もいるはずです。
考えは理解できますが、それほど気にする必要はありません。
顧問弁護士にとってクライアント企業、クライアント企業にとって顧問弁護士は、取引先のひとつです。
別の取引先と契約しても、気にする方は少ないでしょう。
また、多くの弁護士は、事業環境の変化とともに複数の顧問契約を締結する企業が増えていることを理解しています。
必要性を感じる場合は、気兼ねなく検討を進めてみてはいかがでしょうか。
ちなみに、意見を交換してほしいなどの希望がなければ、別の顧問弁護士がいることを伝える必要はありません。
複数の顧問弁護士を活用すると意思決定の質を高められる
ここでは、複数の顧問弁護士がいるメリット、デメリットなどについて解説しました。
主なメリットは、さまざまなアドバイスを受けられることです。
意思決定の質を高められる可能性があります。
主なデメリットは、顧問料の合計金額が高くなることです。ただし、適切に活用すれば、全体のコストを抑えられることがあります。
東京の顧問弁護士・企業法務なら青山東京法律事務所では、企業法務から刑事事件まで幅広い業務への対応が可能です。
また、当事務所の植田弁護士は、前職は外資系コンサルティング会社でしたので、クライアントのビジネスを正確に理解することに長けています。
信頼できる顧問弁護士をお探しの方は、青山東京法律事務所にご相談ください。
監修者

植田 統 弁護士(第一東京弁護士会)
東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士
東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。
野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。
米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。
2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。