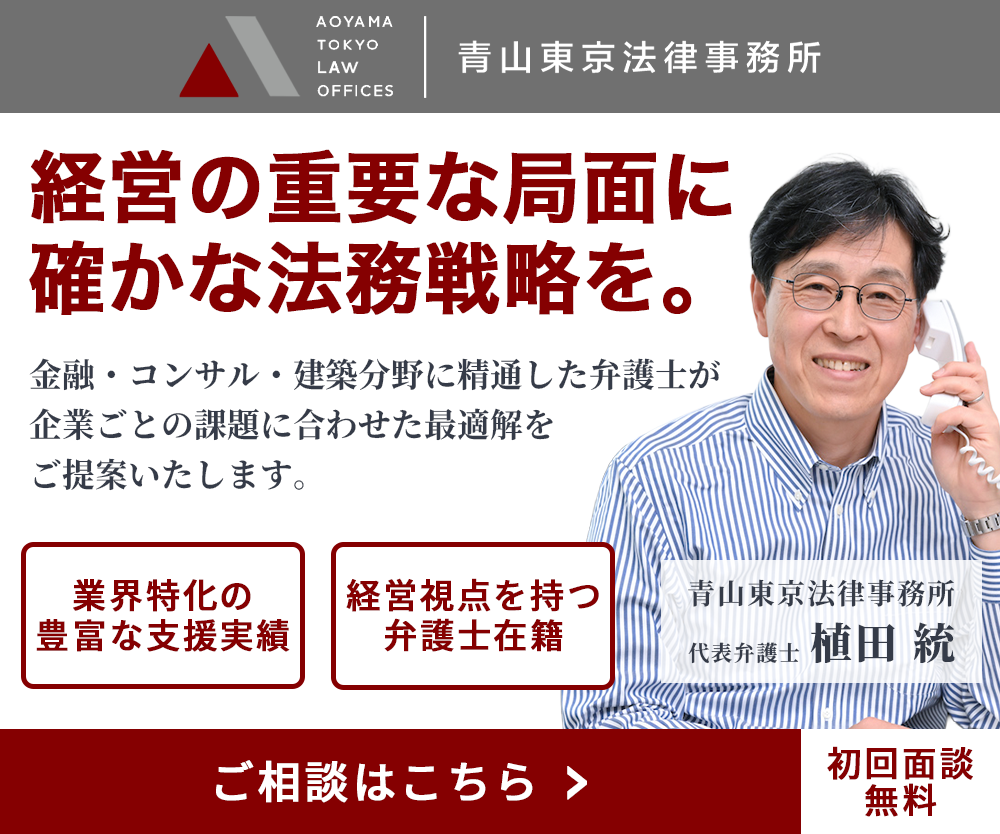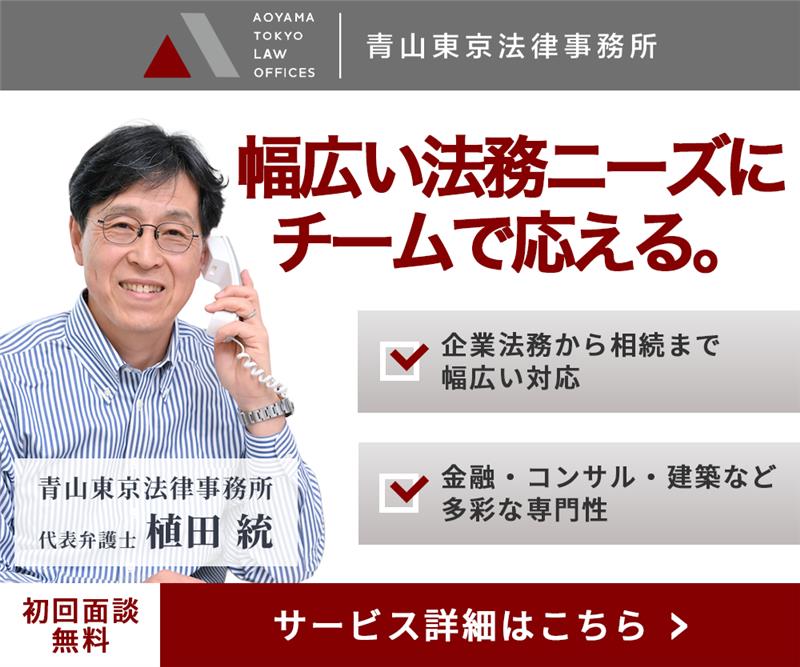公開日: 更新日:
法務デューデリジェンスは、M&Aで実施されることが多い取り組みです。
具体的には、社内規定や契約書、知的財産権などを確認し、対象企業の法的リスクを把握します。
買収の可否や買収価格を決定する判断材料になることもあります。
重要性の高い取り組みといえるでしょう。
ここでは、法務デューデリジェンスの概要、目的を解説するとともに、主な調査項目、調査の流れなどを紹介しています。
以下の情報を参考にすれば、全体像を理解できるはずです。
M&Aを検討中の方は、参考にしてください。
目次
法務デューデリジェンスとは

デューデリジェンス(DD)は、投資や出資を行う前に投資先、出資先の価値、リスクなどを調査することです。
具体的には、以下の種類などがあります。
【デューデリジェンスの種類】
- 法務
- 財務
- 税務
- 人事・労務
- IT
法務デューデリジェンス(以下、法務DD)は、企業の買収・合併(M&A)などを実施する際に、対象となる企業の法的リスクを調査するために実施します。
法務DDの主なチェック項目は次のとおりです。
【チェック項目】
- 会社組織等
- 株式
- 契約内容
- 許認可・法令遵守
- 人事労務
- 訴訟・紛争
- 知的財産権
- 環境問題
これらについては、後ほど詳しく解説します。
(※ここからは特別な記載がない限り、M&Aにおける法務DDを前提とします。)
法務デューデリジェンスの目的

法務DDの主な目的は、売り手企業が抱えている法的リスクを事前に把握・評価することです。
買収後に法的トラブルが発生すると、買い手企業は大きな損失を被る恐れがあります。
売り手企業のコンプライアンス違反で、買い手企業のイメージが悪化する可能性があります。
あるいは、法的リスクを回避できず、企業価値の減少や、事業継続の困難といった事態に発展する恐れもあります。
法務DDの結果は、買収の可否、買収価格、買収条件などに大きな影響を与えます。
法的リスクが大きい場合は、買収を中止することも十分に考えられます。
法務DDは、M&Aの重要なプロセスのひとつです。
法務デューデリジェンスのチェック項目
法務DDでは、次の項目などを主にチェックします。
会社組織等
基本のチェック項目として、会社組織などがあげられます。
チェックする資料の例は以下のとおりです。
【資料の例】
- 定款、社内規定、取締役会規定
- 履歴事項全部証明書
- 取締役会や株主総会の議事録
- 関係会社の登記簿謄本(あれば)
定款などをチェックすると、売り手企業の事業概要や組織体制を把握できます。
履歴事項全部証明書からは、さまざまな情報を読み取れます。
たとえば、所定の期間内に登記すべき事項を登記していない場合、法務機能に問題を抱えている恐れがあるといえるでしょう。
チェックをより慎重に行わなければなりません。
社内規定や議事録を確認すると、売り手企業の意思決定のプロセスがわかります。
また、労務問題、紛争の有無などを間接的に把握できることもあります。
以上のほかでは、コンプライアンス体制の整備状況もチェックしておきたいポイントです。
株式
株式会社を買収する場合、売り手企業の株式もチェックする必要があります。
主なチェックポイントは以下のとおりです。
【チェックポイント】
- 株主の構成
- 株式が有効に発行されているか
- 特別な権限をもつ株式の有無
- 会社と株主間の合意の有無
M&Aでは、売り手が株式を適法かつ有効に保有していることが重要です。
名義株(名簿上の株主と実際の株主が異なる)ではないか、譲渡は適正に行われているかなどをチェックします。
特別な権限をもつ株式、いわゆる黄金株(拒否権などをもつ株式)の有無もチェックしておきたいポイントです。
買収後、ガバナンスの制約を受ける恐れがあります。
同様に、新株予約権についても確認しておくほうがよいでしょう。
持株比率などに影響を与えることがあります。
契約内容
法務DDでは、重要な契約を中心に、売り手企業が締結している契約内容の確認も欠かせません。
リース契約、業務委託契約などを締結して、何かしらの義務を負っていることがあるためです。
また、契約に不利な条項や注意したい条項が盛り込まれていることもあります。
一例としてあげられるのが、チェンジオブコントロール条項(以下、COC条項)です。
COC条項は、M&Aなどで支配権の移転が生じる際に、契約内容に制限などをかける条項と説明できます。
具体的には、契約相手に対する事前通知を必要とする、契約相手の事前承諾を必要とする、契約相手が契約を解除できるなどが考えられます。
COC条項の存在を知らずM&Aを進めると、買収後の事業計画に悪影響が及ぶ恐れがあります。
法務DDで、契約内容をチェックしておくことが重要です。
許認可・法令遵守
売り手企業が、適法に事業を行っているか確認するため、許認可や法令遵守についてもチェックします。
買収後のリスクを回避するために欠かせません。
特定の業種では、事業を行うため法令に基づく届出、登録、許可が義務づけられています。
具体例として、産業廃棄物業や建設業があげられます。
許認可を取得している場合も、取得した時期、有効期限、更新条件などのチェックが必要です。
許認可の条件によっては、買収後に許認可を失ってしまうことも考えられます。
許認可の引継ぎが困難であれば、M&Aの実施について再検討する必要があるでしょう。
法令遵守は、近年になって特に重視されている項目です。
基本的には、法令違反の有無、コンプライアンス体制、行政処分の履歴などをチェックします。
対象となる法令として、独占禁止法、個人情報保護法などがあげられます。
コンプライアンス体制が整っていない場合は、法的リスクが高いといえるでしょう。
ヒアリングなども行いつつ、詳細を把握することが大切です。
人事労務
人事労務も、チェックするべきポイントは多岐にわたります。
主なチェックポイントは次のとおりです。
【チェックポイント】
- 就業規則
- 雇用契約
- ハラスメント対策
- 従業員との紛争
- 未払い残業代の有無
最新の労働法と就業規則、雇用契約を照らし合わせて、違法な点がないか確認することが大切です。
M&Aを検討している場合は、未払い残業代の有無も慎重にチェックしておかなければなりません。
M&Aにともない、一定の退職者が発生するものです。
退職者は、買い手企業に対して遠慮がなくなるので、未払い残業代があると支払いを求めてきます。
過去3年分のタイムカードをチェックしておきましょう。
訴訟・紛争
売り手企業と第三者間の訴訟・紛争もチェックします。
現在進行形で訴訟・紛争が発生している場合は、その内容と過去の判例を確かめて、予想される勝敗、賠償金の額などを検討しておく必要があります。
今後、発生する恐れがあるリスクを評価するためです。
過去の訴訟・紛争を確認しておくことも欠かせません。
詳細に分析して、売り手企業が抱える問題、同様のトラブルが起こる可能性を把握しておくことが大切です。
訴訟・紛争の有無は、買い手企業の意思決定、売り手企業の価値に一定の影響を与えます。
ヒアリングや関連資料などを活用して、詳しく調べておきましょう。
知的財産権
売り手企業が保有している知的財産権も確認しておきたいポイントです。
具体的には、特許や商標などが、売り手企業の名義で適切に登録されていることを確かめておく必要があります。
併せて、期限、更新、取り消しの可能性、自社にとっての価値などもチェックしておきましょう。
買収後の事業に活用できる知的財産権であることが大切です。
訴訟・紛争のリスクも評価しておかなければなりません。
第三者の権利を侵害していることも考えられます。
関連記事:知的財産権侵害の場合の対処法 | 青山東京法律事務所
環境問題
環境問題も、法務DDで確認しておきたい項目のひとつです。
地域住民とのトラブル、環境関連の法令違反、環境汚染による原状回復費用の発生などさまざまなリスクが考えられます。
基本的には、以下の方法で潜在的なリスクを評価します。
【調査の方法】
- 地形図などを活用した調査
- 登記簿謄本による使用履歴の調査
- 所有者などに対するヒアリング
- 売り手企業に対するヒアリング(過去の取り組みを確認)
より詳しく調べるため、専門家に調査を依頼することもあります。
リスクが判明した場合は、対策費用を評価して、買収価格に反映する、M&Aを中止するなどを検討します。
法務デューデリジェンスの進め方
法務デューデリジェンスの所要期間は1〜2カ月程度となります。
原則として、売り手企業と基本合意契約を締結してから実施します(最終合意前後)。
基本的な進め方は以下のとおりです。
①方針・調査範囲の決定
M&Aにおけるデューデリジェンスの目的は、売り手企業が抱えるリスクを明らかにして取引の判断材料にすることです。
法務、財務、人事・労務などさまざまな領域があるため、まずは方針と調査範囲を決定することが大切です。
冒頭で説明したとおり、法務DDは売り手企業が抱える法的リスクを調査するために実施します。
したがって、調査項目は多岐にわたります。
限られた時間、予算の中で実施するケースが多いため、ここでも調査範囲を検討しなければなりません。
調査の方針、範囲にあわせて、調査体制を整えておくこともポイントです。
基本的には、法律の専門家である弁護士に依頼して行います。
M&Aの目的、売り手企業の業種、規模、想定されるリスクなどを踏まえて、調査範囲を決定しましょう。
②資料の開示請求
設定した調査範囲をもとに、売り手企業に対して必要な資料の開示を請求します。
具体的な手段として、資料の名称を記載したリスト、質問事項をまとめたリストを送付することが考えられます。
開示を求める資料の例は以下のとおりです。
【資料の例】
- 定款
- 株主名簿
- 履歴事項全部証明書
- 就業規則
- 売買契約書
- 雇用契約書
- 許認可証
実際に請求する資料は、ケースで異なります。
売り手企業は、自社の価値を下げないため不利な材料になりうる資料を積極的に提出しない傾向があります。
必要な資料を漏れなくリストアップして、提出を求めることが大切です。
資料の開示は、秘密保持の観点から原則としてデータルーム(またはオンライン上のバーチャルデータルーム)で行います。
データルームとは、開示資料を集めた部屋(ホテル、貸会議室の部屋など)のことです。
③資料の分析・検討
開示された資料を分析して、法的リスクなどを検討します。
掲載情報を確認するだけでなく、その情報の意義も理解することが重要です。
たとえば、雇用契約書が存在しない場合、労使トラブルなど、さまざまな問題が生じやすいといえるでしょう。
ただし、法務DDでは限られた時間で膨大な資料を分析し、法的リスクを評価する必要があります。
弁護士をはじめとする専門家と協力しながら作業を行う必要があります。
資料が不足する場合は、追加で開示請求を行います。
実務では、「資料の開示請求」と「資料の分析・検討」を繰り返すことが一般的です。
④マネジメントインタビュー
資料の分析・検討を終えてから、マネジメントインタビューを実施します。
マネジメントインタビューは、経営陣を対象とするインタビューです。
主な目的は、資料の分析で生じた疑問を解消すること、資料の分析だけではわからない点を確かめることです。
後者の例として、取引先との口頭での合意、開示されていない訴訟の存在などがあげられます。
マネジメントインタビューで新たな疑問が生じた場合は、追加で資料の開示請求などを行います。
経営陣から話を聞けるため、法務DDの中でも特に重要なプロセスといえるでしょう。
⑤現地調査
売り手企業を訪問して、現地調査を実施します。
主な目的は、外部に持ち出せない資料や売り手企業の実態を確認することです。
たとえば、記載された施設や人員配置が実際の状況と一致しているか確認します。
書類の情報と現場の状態が、必ず一致しているとはいえません。
現地調査を実施することで、資料上の情報や経営陣へのヒアリング内容を裏付けできます。
⑥中間・最終報告会
法務DDでは、原則として次の報告会を開催します。
【報告会の種類】
- 中間報告会
- 最終報告会
中間報告会は調査中盤から終盤に実施するのが通例です。
主な目的は、調査で得た情報を共有することといえるでしょう。
中間報告会で、軌道修正が図られることもあります。
調査の結果は、最終報告会で提示されます。
明らかになった法的リスクによっては、買収の可否、買収価格などを再検討することがあります。
最終報告会は重要なものの、必ずしも実施しないケースがあります。
中間報告会から修正がなければ、行わないこともあります。
法務デューデリジェンスの費用相場
法務DDは、原則として弁護士などの専門家に依頼して実施します。
かかる費用は、売り手企業の規模、業務の内容、調査の範囲、報告書の記載方法などで大きく異なります。
また、M&Aの法務DDを前提とすると、取引金額によって、DDにかけることができる金額も自ずと限られてきます。
あえて、規模別に法務DDの費用の目安を案内すると、以下のようなものでしょうか。
| 売り手企業の規模 | 費用の目安 |
|---|---|
| 売上5億、従業員数50名 | 80~100万円 |
| 売上10億、従業員100名 | 100~150万円 |
具体的な金額はケース・バイ・ケースで異なってきますので、法務DDを発注する方は、弁護士とよく話し合い、適切な金額で合意することが必要です。
法務デューデリジェンスの注意点
法務DDを実施する場合は、以下の点に注意が必要です。
提供資料だけでなく追加調査を行う
売り手企業から提供された資料だけで、法的リスクを評価しないようにしましょう。
売り手企業は、自社価値を維持したいため不利な情報を自主的に出さない傾向があります。
したがって、提供された資料だけで評価すると、法的リスクを見落としてしまう恐れがあります。
弁護士をはじめとする専門家の意見を参考にしつつ、追加で資料を請求する、マネジメントインタビューを実施する、現地調査を行うなどの方法で、不明点や疑問点を解消することが大切です。
関連記事:顧問弁護士契約の法律相談の範囲 | 青山東京法律事務所
情報漏えいの防止策を徹底する
法務DDでは、外部に漏れると重大な結果を招く恐れがある情報を調査の対象とします。
したがって、情報漏洩防止策を徹底しておかなければなりません。
具体的な方法として、以下の取り組みがあげられます。
【情報漏洩防止策の例】
- 情報管理についての教育を実施する
- 調査に関わる人員を制限する
- 調査の範囲に応じてアクセス権限を設定する
- 資料の閲覧場所を限定する
- 資料の持ち出し、撮影を禁止する
これらの対策を講じることで、情報漏洩のリスクを抑えられます。
M&A前後に必要な届出を確認する
M&Aに必要な手続きを確認しておくことも欠かせません。
提出を忘れると無駄な時間や労力が増え、重大な結果につながる可能性があります。
具体的な届出、手続きはケースでさまざまです。
たとえば、国内売上高200億円超の会社と50億円超の会社が合併する場合は、独占禁止法に基づき公正取引委員会へ事前届出を行っておく必要があります。
弁護士などの専門家に相談して、M&A前後に必要な届出や手続きを確認しておきましょう。
M&Aの法務デューデリジェンスは弁護士に依頼
ここでは、法務DDについて解説しました。
簡単に説明すると、M&Aなどを実施する際に、社内規定、契約書、許認可証などを確認して、売り手企業の価値や売り手企業が抱える法的リスクを調べることです。
企業価値を正しく評価するため、安全に取引するため欠かせないプロセスと考えられます。
調査は、弁護士をはじめとする専門家に依頼することが一般的です。
東京の顧問弁護士・企業法務なら青山東京法律事務所では、これまでに顧問先のクライアントから依頼を受け、多くの法務デューデリジェンスを行ってきました。
製造業、建設業、産廃業等での経験を有しており、迅速かつ的確に実施する体制が整っています。
M&Aで法務デューデリジェンスについて法律事務所をお探しの方は、是非青山東京法律事務所にご相談ください。
監修者

植田 統 弁護士(第一東京弁護士会)
東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士
東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。
野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。
米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。
2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。