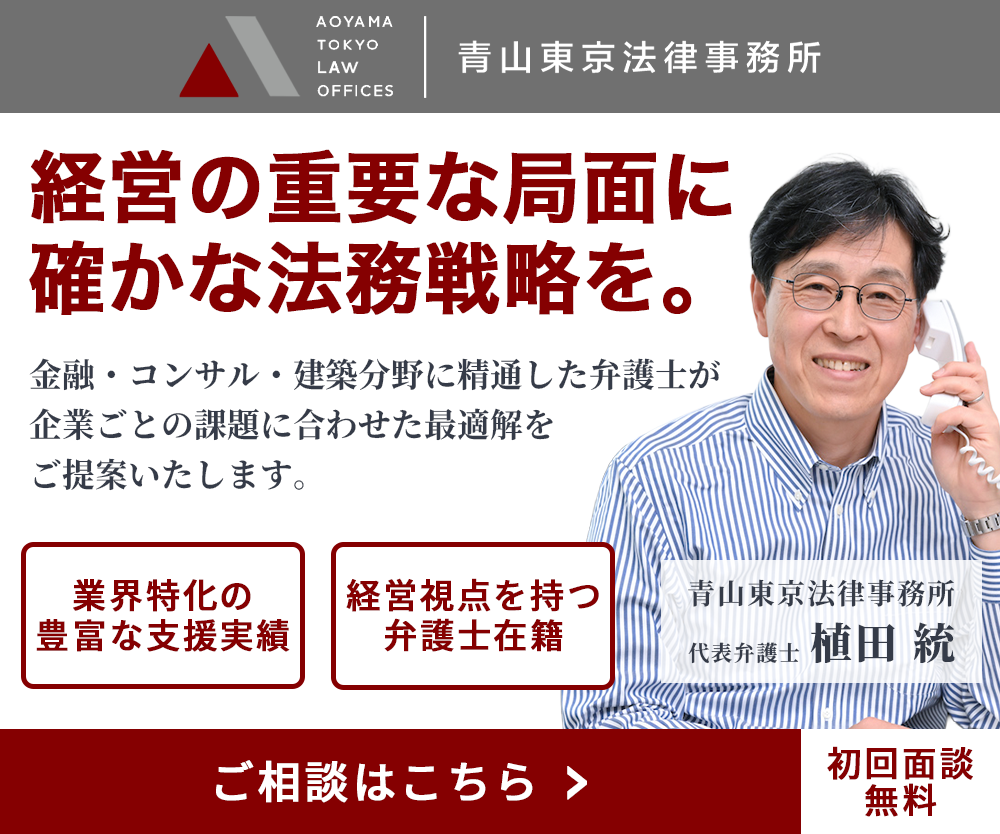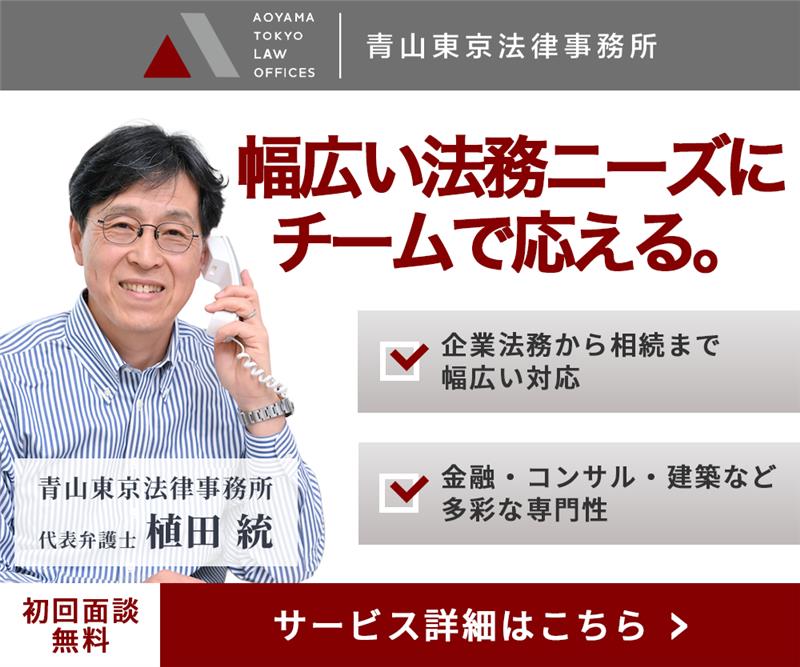公開日: 更新日:
事業への影響を軽減するため、犯罪で逮捕された社員を直ちに解雇したいと考える方は少なくありません。
一見すると正しい行動に思えますが、会社が不利な立場に追い込まれることもあるため、処分を慎重に検討することが大切です。
ここでは、犯罪で逮捕された社員の解雇や身柄拘束中の出勤の取り扱いについて解説するとともに、会社がするべきことや会社が検討するべきことなどを紹介しています。
以下の情報を参考にすれば、社員の逮捕にどのように対処すればよいかがわかるはずです。
想定外の出来事で、お困りの方は参考にしてください。
目次
社員が逮捕されたときに会社がすべきこと

社員が逮捕されたと知ったとき、会社はどのように対応すればよいのでしょうか。
ここでは、連絡を受けた会社がするべきことを解説します。
(1)事件の概要を確認
社員が犯罪で逮捕されたという連絡は、本人のご家族や警察から受けることが多いでしょう。
突然の出来事に動揺してしまいがちですが、まずは落ち着いて事件の概要を確認することが大切です。
社員が業務遂行の一環として行った行為により第三者に損害を与えた場合には、使用者責任が発生して会社にも影響が及ぶ恐れがあります。
使用者責任の説明は以下のとおりです。
(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。引用:e-GOV法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」
事件の概要を把握することは、社員が犯罪で逮捕された会社にとって欠かせない取り組みです。
ちなみに、この段階で社員を解雇することは勧められません。
有罪が確定しているわけではなく、無罪になることや誤認逮捕の可能性も十分に考えられます。
(2)逮捕・勾留場所を確認
並行して、社員が逮捕された場所、その後勾留されている場合にはその場所を確認します。
次のステップで、本人の認識や意向を確かめるためです。
逮捕の段階では、基本的には警察署の留置場で勾留されています。
ここでいう警察署は、原則として事件が起きた場所を管轄する警察署(=現場に臨場した警察官が所属している警察署)です。
逮捕後の勾留も、起訴又は釈放されるまでは、その警察署で行われます。
(3)本人の認識や意向を確認
次に、犯罪についての本人の認識を確認します。
本人が被疑事実を認めているとは限らないためです。
加えて、本人の今後の意向も確かめておかなければなりません。
具体的には、勾留期間中の有給消化についてなどが考えられます。
ただし、逮捕されてから最大72時間(勾留決定が出るまで)は、家族であっても面会できません。
面会できるのは弁護人、弁護人になろうとする者だけです。
勾留が決まると、接見禁止がついているかどうかで、家族、会社関係者が面会できるかどうかが決まります。
共犯がいる組織的な犯罪の場合、本人が否認している場合等は、接見禁止がつけられるケースが多いようです。
接見禁止がついていなければ、家族、会社関係者を含む第三者が会えるようになります。
とはいえ、話せる時間は10~20分程度です。
アクリル板越しの会話になるうえ捜査官も立ち会います。
詳しい話を聞くことは難しいケースが多いでしょう。
また、勾留されている社員と電話やLINE等で連絡を取ることもできません。
したがって、接見禁止がついている場合には、弁護士を介して連絡を取ることになります。
(4)今後の見通しを確認
社員の弁護人とやり取りする際に、今後の見通しについて確認します。
確認しておきたい主なポイントは以下のとおりです。
【確認したいポイント】
- 身柄拘束が続くと考えられる期間
- 起訴される可能性
- 不起訴になる可能性
- 考えられる処分の内容
これらの情報を収集することで、会社側の方針を検討しやすくなります。
出社できない期間がどれくらい続くか、会社にどのような影響が及ぶかなどを予想できるためです。
(5)社員の逮捕がマスコミ報道された場合
マスコミ対応も、会社がやるべきことのひとつです。
自社には関係ないと思うかもしれませんが、SNSが普及しているため、会社の規模を問わず初動を誤ると逮捕の理由によっては炎上します。
この影響で、取引が中止になることも考えられます。
企業名を含めて逮捕の事実が報道された場合は迅速な対応が必要です。
まずは、以下のポイントをまとめて発表するとよいでしょう。
【発表内容】
- 社員が逮捕されたこと
- 情報の把握に努めていること
- 現在も捜査が続いていること
- 事実関係が明らかになってから厳正に対処すること
事業に与える影響を最小限にとどめるため、迅速かつ誠実に対応することが重要です。
ちなみに、速報性を重視する報道の中には、不正確な情報が含まれていることもあります。
マスコミ情報だけで、社員を処分することも勧められません。
社員が逮捕されている間の出勤の取り扱いについて

社員が逮捕されたときに、問題になりやすいのが出勤の取り扱いです。
逮捕された社員は、最大23日間、身柄を拘束されます。
起訴後も、保釈が認められない限り、身柄を拘束される期間が続きます。
以上を踏まえて、本人の意向を確認しておくことが大切です。
本人が希望する場合は、この間に有給を消化します。
有給休暇は労働者の権利であるため、社員が逮捕された場合も本人が申請すれば原則として応じる必要があります。
一方で、会社の意向で有休を強制的に取得させることはできません。
就業規則に逮捕などを理由とする休職の規定を定めている場合は、これを適用して社員を休職扱いにすることも考えられます。
休職期間中の賃金は就業規則の規定によります。
逮捕などを理由とする休職の規定がない場合は、欠勤として扱うことが多いでしょう。
特別な規定を定めていない場合、民法第624条に従い、欠勤期間中の賃金を支払う必要は原則としてありません。
逮捕、勾留について連絡があった場合は、会社の判断で無断欠勤として扱うことは避けるほうが無難です。
社員が逮捕されたら、解雇できるのか?
犯罪で逮捕された社員を解雇したいと考える方は多いでしょう。
ここでは、条件別に解雇の可否を解説します。
(1)直ちに懲戒解雇できるわけではない
逮捕されたことを理由に、社員を直ちに解雇できるわけではありません。
刑事裁判で有罪判決が確定するまで、被告人は無罪と考えられるためです。
また、労働契約法で解雇について次のように定められています。
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
引用:e-GOV法令検索「労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)」
逮捕の事実だけで懲戒解雇をすると、客観的に合理的な理由を欠く、社会通念上相当ではないと判断される恐れがあります。
ちなみに、厚生労働省が発表しているモデル就業規則にも「逮捕」という文言は記載されていません。
モデル就業規則に記載されている懲戒解雇の事由は以下のとおりです。
① 重要な経歴を詐称して雇用されたとき。
② 正当な理由なく無断欠勤が 日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。
③ 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、 回にわたって注意を受けても改めなかったとき。
④ 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
⑤ 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。
⑥ 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。
⑦ 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。
⑧ 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。
⑨ 第12条、第13条、第14条、第15条に違反し、その情状が悪質と認められるとき。
⑩ 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき。
⑪ 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め若しくは供応を受けたとき。
⑫ 私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。
⑬ 正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき。
⑭ その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。引用:(pdf)厚生労働省「モデル就業規則」
嫌疑を受けている事実が、上記の⑤、⑥、⑪、⑫、⑬等に当たる場合にのみ、懲戒解雇の事由となりうるものと思われます。しかし、この時点では、社員が嫌疑をかけられているだけで、有罪が確定した訳ではありませんので、会社としては慎重な対応が必要です。
(2)有罪判決を受けた場合は?
社員が有罪判決を受けた場合も、懲戒解雇が必ず認められるわけではありません。
その理由が私生活上の非違行為で、会社に与える影響が小さい場合は、懲戒解雇の事由に該当しない恐れがあります。
実際に、有罪判決を受けた社員の懲戒解雇を、裁判所が無効と判断したケースもあります。
就業規則のどの項目に当たるのか、懲戒解雇とするほど重要なものか、会社として適正な手続を踏んでいるかなどを考慮することが大切です。
(3)懲戒処分は慎重に検討するべき
ここまでの説明でわかるとおり、懲戒処分は慎重に検討する必要があります。
逮捕後に不起訴になるケースや無罪になるケースなどもあるため、原則として懲戒処分は有罪判決がでてから検討するべきといえるでしょう。
参考に、懲戒処分について争った判例を紹介します。
【小田急電鉄事件】
痴漢撲滅運動に取り組んでいた鉄道会社に勤務する従業員が、痴漢行為により、2度、逮捕されたのち余罪を自白した。鉄道会社は就業規則に基づき懲戒解雇をするとともに退職金の不支給を決定した。解雇された従業員が、懲戒解雇と退職金不支給の適否を争うため提訴。東京高裁は、懲戒解雇を有効、退職金を3割支給するべきと判断した。
出典:公益社団法人全国労働基準関係団体連合会「小田急電鉄(退職金請求)事件」
【ヤマト運輸事件】
ヤマト運輸の運転手が、帰宅途中に飲酒し、自家用自動車を運転している際に酒気帯び運転で検挙された。ヤマト運輸は、業務内、業務外を問わず飲酒運転および酒気帯び運転を懲戒解雇とする規定を定めていたため、これに基づき当該運転手を解雇し、退職金も支払わなかった。当該運転手は、懲戒解雇と退職金の不支給の適否を争うため提訴。東京地裁は、懲戒解雇を有効、退職金を3割支給するべきと判断した。
出典:総務省「民間企業における退職金の取扱い(支給制限率)についての判例」
社員の逮捕後に検討するべきこと

社員が逮捕されたときに、会社が検討するべきことは以下の2点です。
(1)社員本人に対する対処
社員が逮捕された場合は、当該社員に対する対処を検討します。
注意したいポイントは以下のとおりです。
【注意したいポイント】
- 推定無罪の原則に従う
- 懲戒処分を急いで行わない
- 勤務継続の可否を判断する
刑事裁判で有罪が確定するまで無罪と推定されます。
犯罪者と決めつけて、急いで懲戒処分を行わないことが大切です。
有罪判決を受けた場合や本人が犯罪を認めている場合は、懲戒処分の要否を検討しましょう。
想定される勾留期間、処分の内容などを踏まえて、勤務継続の可否を検討しておく必要もあります。
(2)将来の事件発生予防策
会社の信頼や社内の秩序を守るため、再発予防に取り組むことも重要です。
具体的な予防策はケースで異なりますが、以下の点を見直しておくと事件の発生を防ぎやすくなります。
【再発予防策】
- 就業規則、懲戒規定を見直す
- コンプライアンス研修を実施する
- リファレンスチェックを実施する
就業規則、懲戒規定の見直しにより事件の発生を抑えられます。
会社側の視点では、トラブルに対処しやすくなります。
社員を対象とするコンプライアンス研修を実施することも大切です。
ルールを把握していないため、罪を犯してしまうケースもあります。
リファレンスチェックは、採用時に応募者の働きぶりや人間性などを、前職の同僚などからヒアリングする取り組みです。
実施することで、トラブルを遠ざけられる可能性があります。
社員の逮捕によって会社に損害が発生した場合
社員の逮捕により、会社に損害が発生することもあります。
損害賠償請求を行いたくなりますが、必ず認められるわけではありません。
損害賠償請求しにくいケースとしやすいケースを解説します。
(1)損害賠償請求がしにくいケース
以下のケースは、損害賠償請求が認められにくいと考えられます。
【具体例】
- プライベートな理由で社員が逮捕されたため、一時的に業務に支障がでて売上が低下した
- 社員の逮捕でブランドイメージが損なわれて売上が低下した
前者は、犯罪による逮捕と売上低下に明確な因果関係を認められません。
ブランドイメージは、さまざまな要因で損なわれるためです。
逮捕による欠勤の結果としての業務支障と売上低下との因果関係も認められないでしょう。
社員の逮捕と損害の関係を明らかにできない場合は、損害賠償請求をしにくいといえるでしょう。
(2)損害賠償請求がしやすいケース
犯罪行為が業務とかかわっていて、会社に具体的かつ証明可能な損害を与えた場合は、損害賠償を請求しやすいと考えられます。
具体例として以下のものがあげられます。
【具体例】
- 社員が売上金の一部を抜き取っていた
- 社員が商品を持ち出して転売していた
その他にも、業務中の過失による交通事故などで、使用者責任が発生して会社が被害者に賠償金を支払った場合、社員に対する求償権(賠償金の全部または一部の負担を求める権利)を認められることがあります。
ただし、求償が認められる範囲は、ケースにより異なります。
(3)損害賠償と会社の顧問弁護士
逮捕された社員の家族などから、会社の顧問弁護士を紹介して欲しいなどとお願いされることがあります。
当該社員に対して、懲戒処分や損害賠償請求などを検討している場合は注意が必要です。
会社と社員の利益が相反する場合、弁護士は、原則としてどちらか一方の利益しか守れないためです。
会社の顧問弁護士が当該社員の弁護人になると、懲戒処分などを検討するときに相談できなくなってしまいます。
基本的には、別の弁護士を紹介するほうがよいでしょう。
関連記事:顧問弁護士を複数依頼するメリットと検討すべきケース
関連記事:顧問弁護士がいない会社は危険?想定されるリスクを紹介
社員の逮捕に備えた社内体制の整備が大切

続いて、社員の逮捕に備えた会社の取り組みを紹介します。
(1)社員が逮捕されたときのルール作り
社員の逮捕に備えて、就業規則を見直すなど、ルール作りを行っておくことが大切です。
参考に、検討しておきたい主なポイントを紹介します。
【検討しておきたいポイント】
- 弁護士や家族と連絡をとる担当者
- 接見を行う担当者
- 逮捕や勾留を理由とする休職の規定
- 無断欠勤として扱うケース
- 弁明の機会に関する規定
(2)有罪が確定したときの処分方法を定める
有罪判決を受けたときの対応も検討が必要です。
懲戒処分を行うケースや懲戒処分の具体的な内容などを、就業規則などに明記しておきましょう。
業務に関わる犯罪と業務に関わらない犯罪にわけて、ルールを整備しておくことがポイントです。
ただし、実際の対応は慎重に判断しなければなりません。
必要に応じて、弁護士に相談することをおすすめします。
(3)損害賠償の連帯責任を規定した身元保証書を取り交わす
ケースによっては、犯罪で逮捕された社員に対して損害賠償請求をすることもあります。
損害賠償請求金を回収する方法はさまざまですが、当該社員に金銭的な余裕がないことも考えられます。
このようなケースに備えたい場合は、身元保証書の提出を求めるとよいでしょう。
身元保証書は、社員が会社に損害を与えたときに、本人と身元保証人が連帯して賠償責任を負うと約束する書類です。
ただし、2020年4月1日以降に締結した契約は、極度額(上限額)の定めがなければ無効になります(民法第465条の2の2項)。
この点も踏まえて、対策を検討することが重要です。
(4)広報対応の方法を定める
社員が逮捕されたときに広報対応を誤ると、会社まで社会的な信用を失う恐れがあります。
事前に、対応方法を検討しておくことも欠かせません。
参考に、具体的な取り組みを紹介します。
【検討したい取り組み】
- 広報対応にあたる担当者、チームを決めておく
- 広報対応に関するマニュアルを整備しておく
万が一のときに相談できる弁護士を確保しておくことも有効な対策です。
犯罪で逮捕された社員の解雇は慎重に検討
ここでは、犯罪で逮捕された社員の解雇などについて解説しました。
逮捕された社員を直ちに解雇できるわけではありません。
有罪判決を受けた場合も同様です。
業務との関係、会社に与えた影響などを踏まえたうえで、根拠を明確にしてから対処する必要があります。
具体的な対応は、弁護士に相談してから検討するとよいでしょう。
東京の顧問弁護士・企業法務なら青山東京法律事務所では、顧問先の社員が起こした刑事事件への対応、刑事事件に端を発した民事上の不法行為に基づく損害賠償請求、社員に対する懲戒処分へのアドバイス等も取り扱っております。
社員が刑事事件を起こしてしまったが、その対応に困っているという会社の方は、是非青山東京法律事務所へご相談ください。
監修者

植田 統 弁護士(第一東京弁護士会)
東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士
東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。
野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。
米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。
2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。