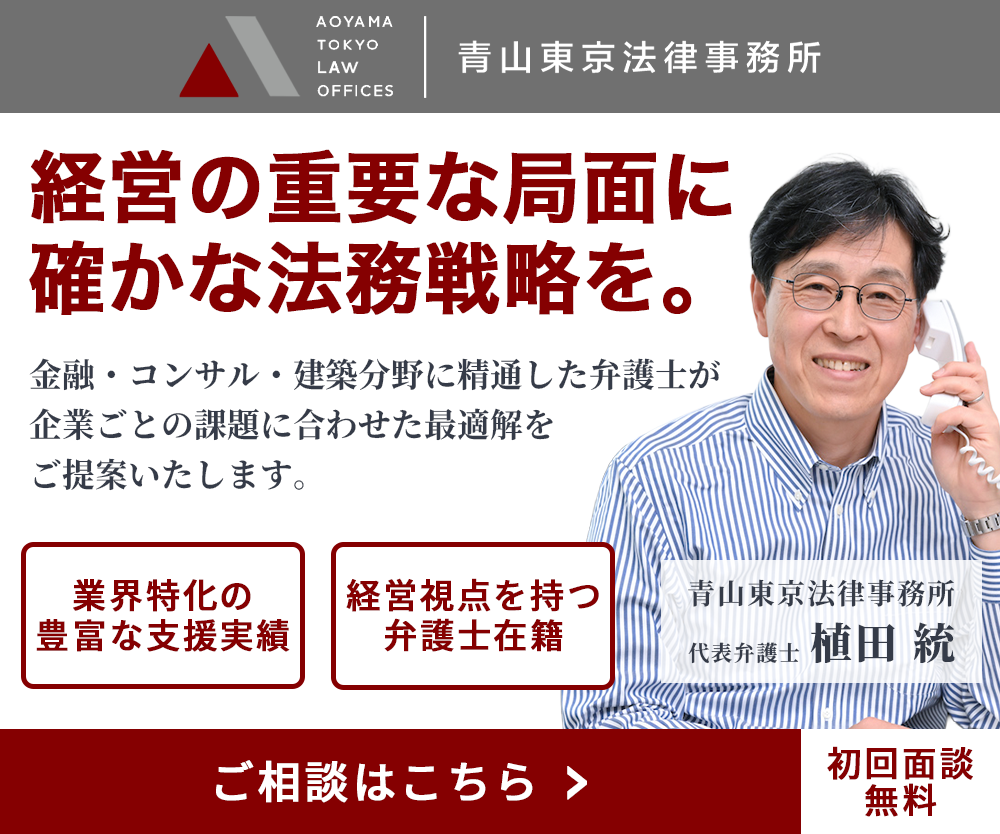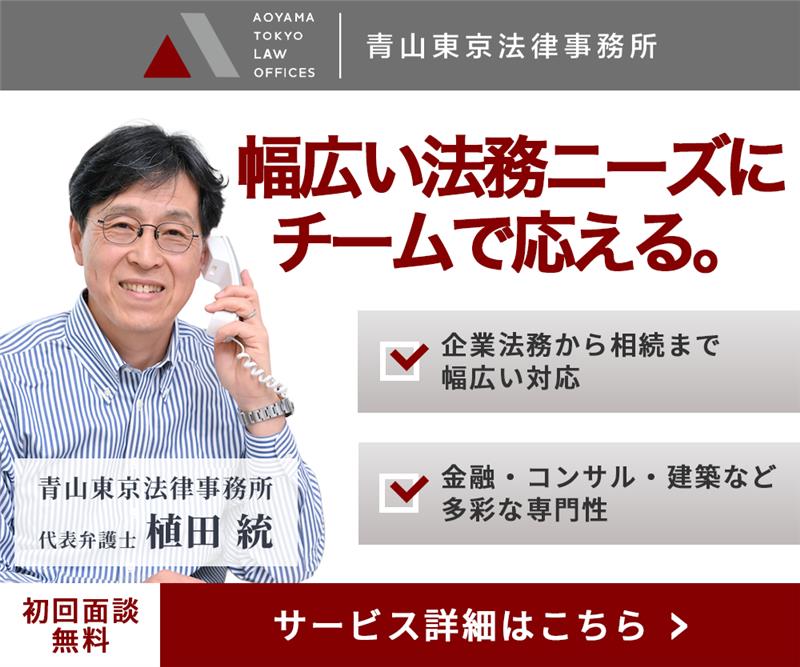公開日: 更新日:
会社経営に伴う大きなトラブルとして挙げられるのが、代金や売掛金の未払に関することです。
こういった債権の回収に関しては、債権回収に関する正しい知識を得ておかなければなりません。
そこで、債権回収とは何か詳しく知りたい方のため、押さえておきたい概要や回収の方法、注意すべきポイントなどについて解説します。
適切な対応をしないことが大きな損失につながってしまうリスクも考えなければなりません。
専門家である弁護士に委託するメリットや費用についても紹介するので、参考にしてください。
目次
債権回収とは

債権回収とは、期限内に支払われなかったお金を受け取る権利である「債権」を回収することをいいます。
実際に現金化するための一連の手続きや活動といったものも含む言葉です。
商品やサービスを提供したものの、相手から代金が支払われないような場合は、その代金を回収する債権回収を行うことになります。
似たような言葉として「物権」がありますが、物権は家や車のようにものを対象とした権利であるのに対し、債権は人に対する請求権です。
債権回収の方法
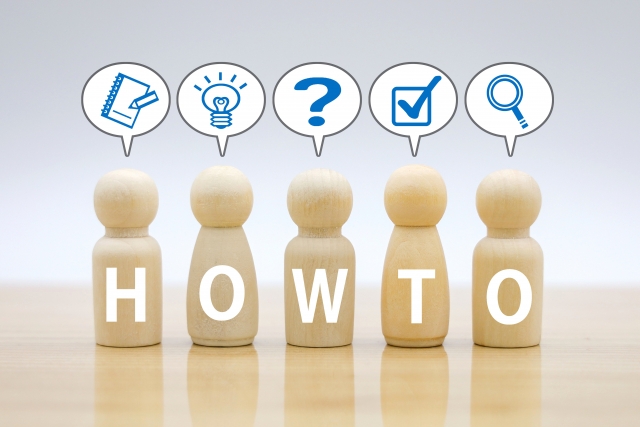
債権回収には、実にさまざまな方法があります。
状況に合わせて適切なものを選んでいかなければなりません。
ここでは、代表的な債権回収の方法について7つ紹介します。
電話や対面での交渉
直接話し合いができる場合は、電話や対面での交渉を行っていくことになります。
ただし、債務者に支払いの意思がない場合は難しいといえるでしょう。
電話やメール、対面での交渉を求めたものの応じてもらえない場合は、弁護士のような専門家に協力を仰ぎながら話を進めていくこともあります。
内容証明郵便の送付
内容証明郵便を送り、支払いを催促する方法もあります。
内容証明郵便とは、郵便局がいつ・誰から・誰へ送った郵便なのかを証明するものであり、相手先に確実に通知したという事実を証明できるのが特徴です。
そのため「そのような書類は受け取っていない」と言い逃れされてしまうのを防げます。
弁護士から出してもらった方が相手方に対してインパクトがありますが、本人で進めることも可能です。
関連記事:内容証明郵便とは|期待できる効力と記載事項・発送までの流れ
支払督促
債権者が支払い督促の申し立てを行い、裁判所が支払いを催促するのが支払督促と呼ばれる手続きです。
債務者が支払督促正本を受領した日から2週間以内に、督促異議の申し立てを行わないときは、債権者は仮執行宣言の申立てを行うことができます。
債務者に仮執行宣言正本が送達されてから2週間以内に督促異議の申し立てをしないときは、仮執行宣言付支払督促が確定します。
その後も債務者から支払いがないときは、債権者は強制執行を行うことが可能になります。
強制執行とは、債務者が所有している財産を差し押さえ、それを換金したり処分したりすることで債権の弁済に充当する手続きのことです。
裁判を行うのと比較して簡便かつ迅速に手続きを進められますので、本人で追行することが可能です。
ただし、債務者が異議を申し立てた場合には、通常訴訟へと移行していくことになります。
訴訟
裁判所に対し正式な訴えを起こし、裁判を通じて債権の有無や金額を確定する手続きが訴訟です。
相手が電話や対面での交渉に応じない、支払督促に異議申し立てをしたといった場合に選択されます。
手続きは複雑で時間や費用がかかることもありますが、相手方が争わないケースについては、1回目または2回目の裁判期日で判決が出るケースも珍しくありません。
訴訟を提起することになるので、原告による裁判所への訴状の提出、裁判所による被告への訴状の送達、裁判所での口頭弁論などが行われることになります。
債権者本人の訴訟も可能ですが、手続の複雑性から見ると、弁護士に依頼した方がスムーズに手続が進められます。
仮差押え
仮差押えとは、支払い督促や訴訟をやって確定判決などの債務名義(裁判所に強制執行を申し立てる資格を示す文書)をもらう前に、仮に相手方の資産を押さえ、使い込まれないようにしてしまう手続のことです。
これは、債権回収の相手方は資力に乏しい場合が多く、支払い督促や訴訟などの手続を進めている間に、資産隠しをされたり、使い込まれてしまう可能性が高いので、その前に相手方の不動産や預金を押さえ、最終的に訴訟で勝った時に回収できるようにしておくための手続です。
強制執行
これに対し、強制執行とは裁判所の判決や支払い催促が確定した後、裁判所が強制的に差し押さえた債務者の財産から債権を回収する手続きのことをいいます。仮差押えに対して、本執行と呼ばれることもあります。
いくら債務者が支払いを行わないからといって、勝手に会社や自宅に乗り込み、換金できそうなものを持ち出すことはできません。
一方、強制執行は法律上の手続きであるため、正当な形で相手方の財産を処分し、債権を回収する行為が認められることになります。
大きく分けると、不動産が対象となる不動産執行と、在庫や設備が対象となる動産執行、預金などが対象となる債権執行の3つです。
差し押さえ対象は給料や預金、不動産など多岐にわたりますが、そもそも回収できる財産がない場合は効果がありません。
債権回収をするときの注意点

債権回収を行うにあたり、気をつけておかなければならないポイントがあります。
特に以下の3つはよく確認しておきましょう。
契約内容と支払履歴を確認する
実際に債権回収を行動に移す前に、契約内容と支払い履歴の確認を行いましょう。
現在、債権が具体的にどのような状況になっているのか確認が必要です。
支払いが遅れている金額や期間についても確認が必要です。
たとえば、相手が部分的にでも支払っている場合は、その金額についても明確にしておかなければなりません。
曖昧な部分があるとトラブルの元になってしまうこともあるので、各種重要な証拠書類などは整理しておきましょう。
債権の消滅時効を確認する
債権がいつ消滅時効を迎えるのかについては、早い段階で確認しておかなければなりません。
消滅時効が完成すれば、債権は回収できなくなります。
確認した結果、契約内容によっては、未回収となっている債権が消滅時効を迎えそうになっているケースもあるでしょう。
このような場合は、時効の完成を妨げるために、内容証明郵便で支払いを督促しておくことが必要になってきます。
2020年3月31日以前に発生した債権については債権の種類ごとによって消滅時効期間が異なりましたが、2020年4月1日に施行された現行民法では、以下のように定められています。
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
この2つのうち、消滅時効の完成が早い方が適用される形です。
たとえば、上記の「一」については、支払い期日が到達すれば債権回収の権利を行使できるようになるので、支払い期日が到来してから5年間でその債権が消滅することになります。
「二」については、明確な支払い期日を決めていない場合などが対象です。
たとえば、債務者から「○○の状況になったら返済する」といった形で曖昧に伝えられており、該当する状況になったのを債権者が3年後に知ったとします。
すると、ここから5年が経過すると消滅時効が完成する形です。
また、債権者が知らないまま10年が経過した場合についても消滅時効が完成します。
消滅期限を迎えないうちに回収できるように取り組んでいかなければなりません。
分割払いの対応を検討する
債務者の状況によっては、一括での支払いを求めるのが困難なケースもあります。
こういった場合は、無理に一括での支払いを求めると対応してもらえない可能性が高いため、分割払いを受け入れることについても検討してみるとよいでしょう。
取り決めた内容については明確に文書で証拠を残しておきます。
また、分割払いが滞った場合の対応に関してもあらかじめ決めておきましょう。
債権回収は専門業者や弁護士に委託すべき?
債権回収を自社で対応しようと考えると、非常に難しいケースもあります。
できれば専門業者や弁護士に委託することを検討してみてはいかがでしょうか。
専門家ということもあり、自社でよくわからないまま債権回収に向けて行動を起こすよりも効果的な対応が期待できます。
デメリットとして費用がかかることが挙げられますが、自社で対応したところ適切な形で行動できず、1円も回収できなかったというケースも少なくありません。
こういった事態を防ぐためにも専門業者や弁護士に委託することをおすすめします。
債権回収を弁護士に委託するメリット

債権回収の成功率を高めたいと考えているのであれば、弁護士への委託も検討してみるとよいでしょう。
委託によって以下のようなメリットがあります。
関連記事:顧問弁護士にかかる費用相場は?依頼する業務内容別にチェック
メリット①相手にプレッシャーをかけられる
弁護士は法律の専門家であり、弁護士名義での連絡は相手に強い心理的圧力を与える効果があります。
実際に、企業の担当者から相手先に電話やメッセージなどで連絡をしても全く反応がなかったものが、弁護士名義で連絡をしたところ一気に進展が見られるケースもあります。
弁護士は代理人として対応が可能であるため、相手にプレッシャーをかけて債権回収を進めたいと考えている場合にも大きなメリットがあるといえるでしょう。
また、弁護士が介入することにより「債権者が本気で回収のために動き出している」という気持ちを債務者が抱くことにつながります。
弁護士の名前が出てくることによりどの程度のプレッシャーを与えられるかについては債務者の経済状況や性格によっても異なりますが、大きな効果につながることもあります。
メリット②弁護士間の話し合いで回収できる可能性がある
当事者同士の話し合いだと、気持ちが高ぶって話し合いで余計な発言をしてしまったりうまくいかなくなったりすることがあります。
一方、債務者側も弁護士に委託している場合は、こちらの弁護士と債務者側の弁護士での話し合いにより、回収が可能になることも珍しくありません。
相手方にも弁護士がついている場合、不利になると懸念する方もいるかもしれません。
ですが、専門家同士で話し合いを行うことにより、冷静かつ合理的な決断が可能となり、迅速かつ公平な解決を図ることが可能になります。
メリット③仮差押え→裁判→強制執行の流れを迅速に進めてもらうことができる
弁護士は、法律や法的手続きに関する専門家です。
弁護士は、債権回収を進める第一段階として、仮差押えを考え、その後で訴訟を起こし、最後に強制執行を行うことで回収の確率を高めていきます。
前述しましたように、仮差押えを行っておくことで、相手方が財産を遣い込んでしまったり、隠匿してしまうことを防ぐのです。
複雑な手続を迅速に進めていかなければならないので、なかなか債権者本人では進めていくことができません。
債権回収を弁護士に委託する場合の費用
弁護士に債権回収を委託した場合にかかる費用は、成功報酬(報酬金)によって大きく変わってきます。
かかる費用の内訳は、以下の3つです。
着手金 依頼するにあたり事前に支払う弁護士費用。経済的利益の額にリンクする。
300 万円以下の場合 8%
300 万円を超え3000 万円以下の場合 5%+9 万円
3000 万円を超え3 億円以下の場合 3%+69 万円
3 億円を超える場合 2%+369 万円
※着手金の最低額は10 万円
成功報酬 債権回収に成功した場合に支払う報酬。獲得した経済的利益の額にリンクする。
300 万円以下の場合 16%
300 万円を超え3000 万円以下の場合 10%+18 万円
3000 万円を超え3 億円以下の場合 6%+138 万円
3 億円を超える場合 4%+738 万円
実費 郵便代、印刷代、交通費など
現在では、上記の料率に従う必要はなく、担当弁護士との話し合いで報酬を決めることができますので、納得できる金額で契約することができます。
また、費用負担が多い場合については分割払いでの相談ができることもあります。
債権回収は専門家に相談することが大切
債権回収の概要や注意点について解説しました。
回収を進めていく際の流れなどをご理解いただけたかと思います。
自社で対応が難しい場合は、弁護士などの専門家を頼りましょう。
相手への心理的圧力を与えられるほか、裁判や強制執行を見越した対応もしやすくなります。
東京の顧問弁護士・企業法務なら青山東京法律事務所では、債権回収について多くの実績があり、仮差押え→訴訟→差押えという手続を迅速に進めることができます。債権回収について弁護士事務所に相談したいと考えているのであれば、青山東京法律事務所までご相談ください。
監修者

植田 統 弁護士(第一東京弁護士会)
東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士
東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。
野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。
米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。
2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。