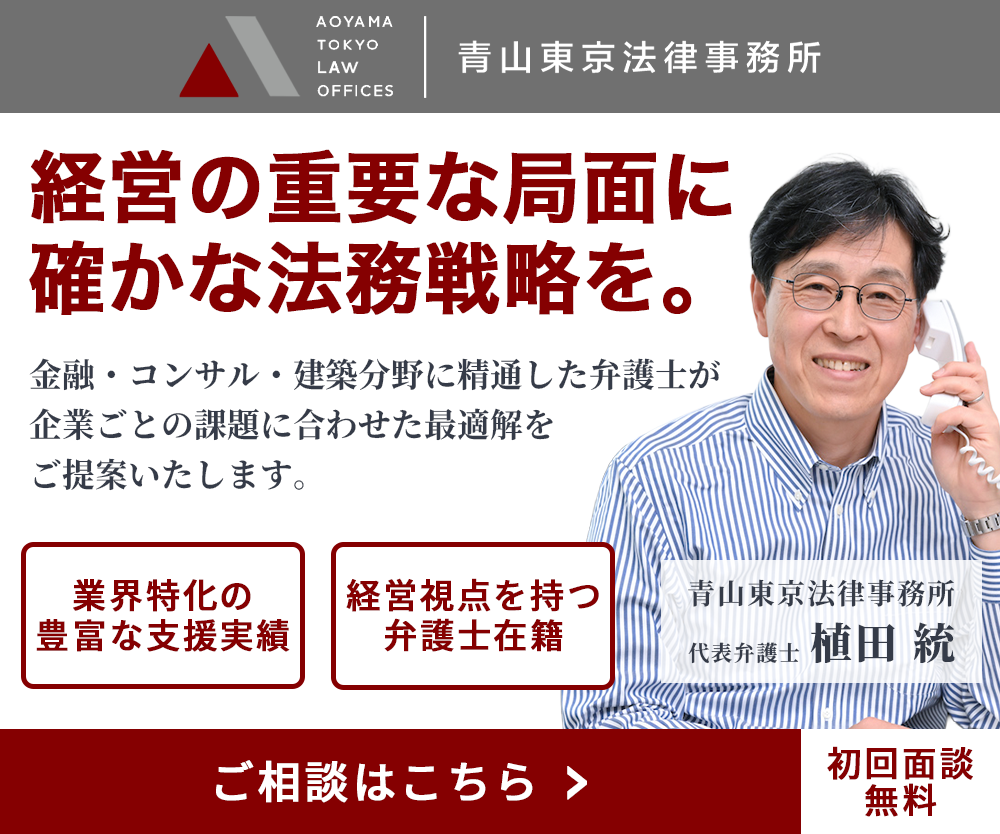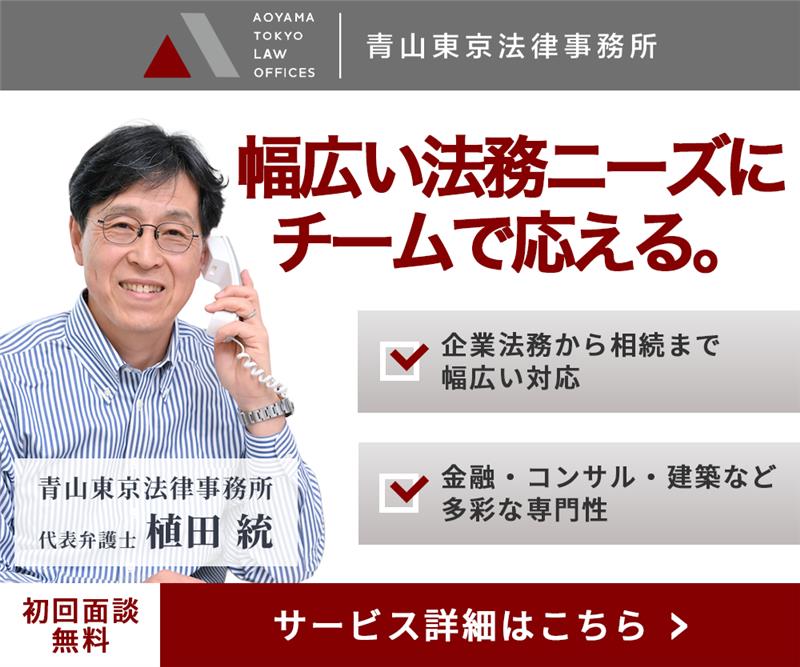公開日: 更新日:
代表取締役の経営判断などに問題がある場合、取締役や株主は、健全な経営を行うために“解任”という選択肢をとることができます。
ただし、解任は簡単に行えるものではありません。
手順を踏んだうえで、万が一のリスクヘッジを行う必要もあります。
そこで本記事では、代表取締役を解任する流れや、必要な準備などを解説します。
「代表取締役の解任を滞りなく進めたい」とお考えの取締役や従業員の参考となれば幸いです。
目次
代表取締役の解任とは

代表取締役から代表権と取締役の地位を失わせることを“代表取締役の解任”といいます。
後述する“解職”では平取締役として会社に籍が残った状態になりますが、解任では平取締役の地位も失います。
なお、解任について知るには、まず代表取締役について正しく把握する必要があるため、その点も改めて整理しましょう。
代表取締役とは、取締役のなかから選ばれた特別な取締役のことで、会社を代表する権限をもっています。会社を代表して契約の締結をしたり、株主総会の招集などを行うことができます。
また、多くの会社では代表取締役=社長となっており、業務執行の最高責任者にもなっています。取締役会で決められた経営方針に基づき、会社を指揮して、それを実現していく役割を担っているのです。
このように、代表取締役は企業にとって非常に重要な存在であることがわかります。
だからこそ、職務への不適任によって会社に損害を与える可能性が高い場合や、持病の悪化などのやむを得ない事情で職責を果たせない場合は、解任しなければならないのです。
解職と解任の違い
解任とよく似た言葉に“解職”がありますが、両者は意味が大きく異なります。
代表取締役の解任は、前述の通り、株主総会において、代表権と取締役の地位の両方を失わせる手続きです。
対し、解職は、取締役会において、代表権のみを失わせ、平取締役に降格させることを指します。
つまり、解任の場合は該当人物を会社から去らせる一方、解職では取締役として会社に残らせることができるのです。
なお、代表取締役解職の取締役会決議に本人がかかわることはできません。
さらに、普段の取締役会で代表取締役が議長を務めている場合は、解職の決議に際して議長もほかの取締役に交代する必要があります。
これは、自身の解職決議において代表取締役は「特別利害関係を有する」、つまり判断に私心が含まれてしまう可能性があるためです。
会社の公正性・健全性を担保するために、このような決まりとなっています。
【ケース別】代表取締役の解任手続きの違い

代表取締役を解任するにあたり必要な手続きは、会社の状況により異なります。
以下で、3つのケース別にそれぞれの流れを解説します。
【ケース別】代表取締役の解任手続きの違い
- ①取締役会設置会社(一般的なケース)
- ②取締役会非設置会社の場合(例:中小企業)
- ③特定の株主が議決権の100%を有しているケース
①取締役会設置会社(一般的なケース)
会社法の定めにより取締役会を設置しなければならない会社、あるいは取締役会を設置している会社の場合は、まず代表取締役の“解職”を行い、そのあと解任に移ります。
これは、もっとも一般的なケースです。
具体的な流れは以下をご覧ください。
取締役会設置会社での代表取締役解任の流れ
- 取締役会を招集する
- 解職決定の投票を行う
- 代表取締役がいなくなった場合は、新たな代表取締役を決める
- 取締役会議事録を作成する
- 各種変更手続きを行う
- 元代表取締役に、取締役の辞任を促す(または放置する)
まず、取締役会の1週間前までに取締役全員に招集通知を送ります。
招集に関する具体的な流れは、会社法の定めに則りましょう。
ただし、取締役会を招集できる取締役が定款などにより定められている場合、招集権のない取締役は自由に取締役会を招集することができません。
このようなケースでは、招集権限のある取締役に対して、取締役会の目的を示せば、取締役会の招集を請求できる旨が会社法366条2項にて定められています。
ただし多くの企業では、代表取締役に取締役会の招集権があることが一般的であるため、解職・解任を目的とした取締役会を招集してもらえることはあまり現実的ではないでしょう。
そこで、実務上は、元々予定されている定例の取締役会で緊急動議として、代表取締役解職決議を提案するという方法が取られます。
この方法によると、それまで議長として議案を仕切っていた代表取締役に特別利害関係がある決議ということになりますので、緊急動議を提案した取締役は、代表取締役の退席を求めることができます。
これにより、代表取締役派の票は1票少なくなります。議案の審議においても、代表取締役派の意見が弱くなることを意味します。
取締役会が10名で構成されていたとすれば、1名減って9名となりますから、5票で解職決議が可決されることになります。
中小企業に多い3名の取締役会の場合には、2名の取締役となり、2票で可決することになります。つまり、緊急動議を発した取締役プラス1名の賛成でよくなります。その上、代表取締役自身はその場にいないのですから、決議が成立する確率は非常に高くなります。
なお、代表取締役が一人しかいない状態で解職した場合は、会社に代表取締役がいない状態となってしまいます。
そのため、あらかじめ「新たな代表取締役の選任」も議案に入れたうえで、取締役会で選任決議を行い、後任者を選出しなけらばなりません。
この時は、代表取締役を解職された取締役は、一取締役として議決に参加することが出来ます。
先ほどの10名の取締役会なら、解職された取締役を入れて10名での審議となりますので、解職を主導した取締役の意中の人が代表取締役に選出されるとは限りません。
代表取締役の解職と新代表取締役が決まったら、登記内容変更手続き、税務署や金融機関での代表者変更手続きなど、法的な登記情報や文書などで必要な各種手続きを行います。
なお、この段階で決まっているのはあくまでも代表取締役の“解職”であり、平取締役としての籍は残っている点にご注意ください。
代表取締役としての職を失うと同時に、本人が自ら取締役としての地位も辞任するケースはよくありますが、そうでない場合は任期満了まで待つ必要があります。
任期が満了した状態で、その取締役が再任されなければ退任となります。
以上が、取締役会設置会社が代表取締役を解任する流れです。
②取締役会非設置会社の場合(例:中小企業)
取締役会を設置していない会社で代表取締役を解任する場合、代表取締役を選んだ方法によって必要な手順が異なります。
まず、代表取締役を互選で選んだ場合は、取締役の過半数が賛成すれば解職できます。
これは、先述の取締役会設置会社の場合と概ね同じ方法です。
解職が決まったら、取締役を辞任してもらうか、任期満了まで待つことで解任となります。
一方、滅多にありませんが、代表取締役を定款で定めている場合は、株主総会で、出席した株主のうち2/3以上の賛成を得る「特別決議」を行わなければなりません。
定款に書かれている代表取締役を別の人物に変える、つまり「定款変更」を実現するには、出席した株主の2/3以上の賛成が必要であるためです。
また株主総会で代表取締役を選んだ場合は、代表取締役解任の普通決議を行います。
この2つのケースでは、決議の結果、代表取締役の解任が決まったら同時に取締役としての地位も失うことになります。
そのため、前述したケースのように改めて辞任を待つ必要はありません。
株主総会を終えたら、議事録を作成しましょう。
なお、株主総会の招集は一般的に、代表取締役が行うことになっています。
しかし自身を解任するための株主総会を、本人が招集することは現実的にあまり考えられません。
そのようなときは、特定の条件を満たした株主(※)が取締役に株主総会の目的事項と招集理由を説明すれば、株主総会の招集を請求できます。
また万が一、株主が請求したにもかかわらず招集の手続きがされない、あるいは請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする招集通知が発せられない場合は、裁判所の許可を得れば自ら株主総会を招集することが可能です。
※……総株主の議決権のうち、3%以上の議決権を6か月前から有している株主(定款により、これを下回る条件が定められている場合は定款に則る)
関連記事:株主総会とは
③特定の株主が議決権の100%を有しているケース
特定の株主が議決権の100%を有している会社ならば、その株主の一存で解任が可能です。
株主総会の一度の決議で、取締役のみならず代表取締役の資格も同時に失わせることができます。
代表取締役を解任するための準備

上記でお伝えした流れで代表取締役を解任するには、事前の準備が必要です。
以下の内容をご確認のうえ、準備を進めましょう。
代表取締役を解任するための準備
- 取締役・株主ヘの根回し
- 解職理由の確認
- リハーサルや書類・印鑑の準備
取締役・株主ヘの根回し
取締役会設置会社で代表取締役を解職するには、取締役会で過半数の賛成を得る必要があります。
そのため、あらかじめ解職に賛成してくれる取締役を探し、根回しを済ませておきましょう。
また、取締役会非設置会社で、株主総会の決議をもって代表取締役の解任を考えている場合には、同様の理由で大株主への根回しが必要です。
いずれの場合でも、代表取締役本人に悟られないよう、慎重に動かなければなりません。
特に、相談した相手が代表取締役派の取締役/株主だった場合、情報が本人のもとへ届いてしまうおそれがあるため、根回しの相手は慎重に選ぶことが大切です。
解職・解任理由の確認
改めて、代表取締役を解職・解任させるべき理由を整理する必要があります。
なぜなら、正当な理由なく代表取締役を解職すると、会社法339条2項の類推適用により、本人から会社に対して損害賠償が請求される可能性があるためです。
第三百三十九条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
引用元:e-GOV法令検索「会社法(平成十七年法律第八十六号)」
正当な理由を整理したうえで、証拠も十分に準備しましょう。
リハーサルや書類・印鑑の準備
当日の解職決議をスムーズに進めるために、解職・解任賛成派の取締役で事前にリハーサルを済ませておくことが望ましいです。
リハーサルは自社の施設内で行うと情報が漏れるおそれがあるため、一般的には貸会議室や法律相談事務所の会議室などで夜の時間帯に行います。
また事務手続きが円滑に進むよう、登記関係の書類を用意したうえで、役員には押印するための印鑑を持参するよう伝えましょう。
ほかに上場企業の場合は、プレスリリースや臨時報告書も準備しておく必要があります。
代表取締役解任後に必要な手続き
代表取締役の解職・解任が決まったあとも、必要な手続きが残っています。
解職・解任後の動きをスムーズに進めるためにも、以下をご確認ください。
解職・解任後に必要な手続き
- 代表取締役の解職を登記する
- 解任した代表取締役に解任通知を送る
- 解任した代表取締役に退職金を支払う
代表取締役の解職を登記する
解職が決まったら、登記変更を行います。
法律上は「解職決議から2週間以内」とされていますが、実際は金融機関などへの登記事項証明書の提出が必要になるため、解職決議の当日に済ませておくのが望ましいです。
代表取締役の解職・解任を登記する際は、法務局に以下の書類を提出しましょう。
代表取締役の解職・解任にあたり提出する書類
- 登記申請書
- 株主総会議事録
- 株主リスト
弁護士や司法書士などの代理人に手続きを依頼した場合は、上記のほかに委任状も提出します。
解任した元代表取締役に解任通知を送る
解任した元代表取締役に、解任通知を送付します。
法的な義務はありませんが、後々のリスクヘッジのために送付しておくと安心です。
具体的には、決議に本人が欠席していた場合、解任通知を送付することで、その事実を知らずに引き続き代表取締役として行動してしまうリスクを避けられます。
解任した代表取締役に退職金を支払う
解任した代表取締役に退職金を支払う旨が、株主総会で承認されている場合は、退職金を支払います。
なお、承認されていない場合は支払う必要はありません。
代表取締役を解職・解任する場合のリスク

代表取締役を解職・解任する際、以下のようなトラブルが発生する懸念もあります。
トラブルを想定したうえで適切に動くために、あらかじめ把握しておきましょう。
代表取締役による多数派工作
解職・解任の動きが代表取締役に悟られた場合、ほかの取締役や株主に対して多数派工作が行われる可能性があります。
代表取締役自ら事前に根回しすることで、賛成する人数を減らすということです。
これが行われると、解職・解任させることができません。
このようなトラブルを防ぐには、代表取締役に動きが知られないように徹底することが一番です。
取締役会で解職決議を行う場合は、先述したように代表取締役派ではない取締役に声をかけたうえで、事業所以外の場所でリハーサルを行いましょう。
また、取締役会の招集通知には議題を記載せず、当日に緊急動議として解職決議を行うという方法も有効です。
なお、“黄金株主”とよばれる、拒否権付き株式(黄金株)を持っている株主がいる場合は、黄金株主への根回しも考える必要があります。
仮に取締役会や株主総会で代表取締役の解職が決まっても、黄金株主が反対すれば不成立となるためです。
正当な理由のない解任としての損害賠償請求
代表取締役の解職・解任に正当な理由がなければ、解職した元代表取締役から損害賠償請求を受ける可能性があります。
損害賠償金の請求額は一般的に、以下の額となります。
解職した代表取締役の残りの任期分の役員報酬+「任期満了まで務めた」と仮定した場合の退職金
高額となるおそれもあるため、企業としては可能な限り避けたいところです。
損害賠償請求を受けるのは、「正当な理由がない場合」なので、解職・解任となり得る正当な理由をきちんと整理し、証拠を集めておくことが望ましいです。
また、代表取締役本人が主張する内容も想定したうえで、反論も準備しておくとよいでしょう。
代表取締役とのトラブルを避ける方法
上記でお伝えしたようなトラブルを避ける方法としては、いくつかの選択肢が挙げられます。
まず、代表取締役の任期満了まで待ち、再任しないという方法です。
この方法であれば、解職・解任のための取締役会や株主総会は不要で、それに伴うさまざまなリスクヘッジの必要もありません。
あるいは、代表取締役本人が自発的に辞任するようにはたらきかけるという方法もあります。
もし事態が深刻で、可能な限り早く解職・解任させたいのであれば、弁護士に相談したうえで解職決議の準備を進めることをおすすめします。
法的な観点から、トラブルに発展するリスクの低い方法の提案を受けられるためです。
任期満了を待たずに代表取締役を解任させるには、解職の決議を行う必要がある
今回は、代表取締役を解任する方法についてお伝えしました。
取締役会設置会社であれば、取締役会で解職の決議を行えば代表取締役の解職が可能です。
また取締役会非設置会社であっても、必要な手順を踏めば任期満了を待たずに解任できます。
なお、代表取締役の解職・解任には損害賠償請求などのトラブルに発展するリスクがある点にご留意ください。
スムーズに事を進めたいのであれば弁護士に相談されることをおすすめします。
東京の顧問弁護士・企業法務なら青山東京法律事務所では、これまでにたくさんの取締役間の紛争案件を取り扱ってきましたので、取締役の解任等のトラブルを抱えている会社の方は、ぜひ青山東京法律事務所までご相談ください。
代表取締役の解職・解任をお考えの際は、お気軽にご相談ください。
監修者

植田 統 弁護士(第一東京弁護士会)
東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士
東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。
野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。
米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。
2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。