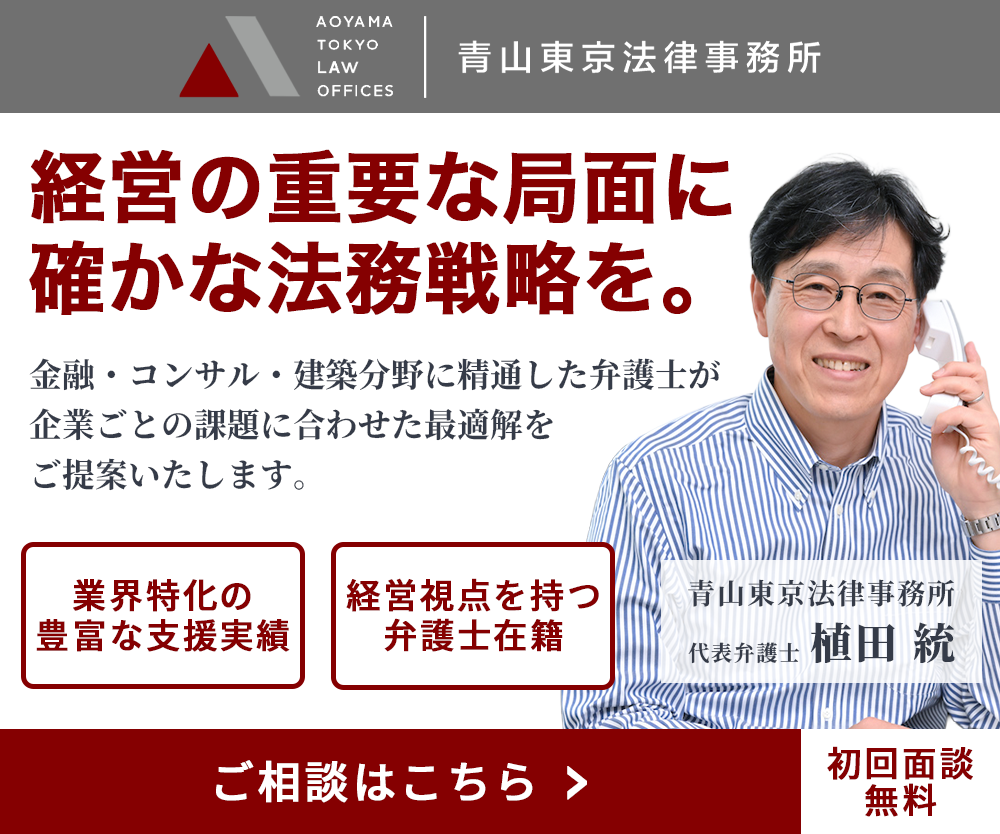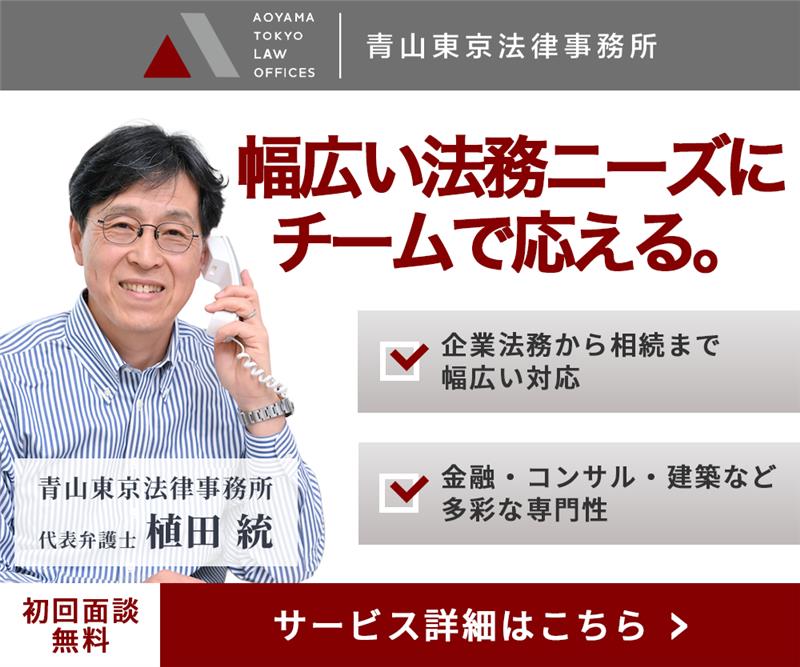公開日: 更新日:
顧問弁護士の選び方に悩んでいませんか?
「誰に相談すればよいのか分からない」
「どの基準で判断すべきか曖昧」
など、そんな不安を抱える経営者も多いはずです。
自社に適した弁護士が見つからず、依頼先に悩む企業担当者も少なくありません。
顧問弁護士は、企業の安定的な成長を支える重要なパートナーです。
企業法務に関する知識・経験などを確認したうえで、慎重に選任する必要があります。
ここでは、顧問弁護士の役割や選び方に加え、選任時の注意点についても解説します。
契約締結を検討している方は参考にしてください。
目次
顧問弁護士の役割

顧問弁護士は、企業などと契約を結び、相談に応じる弁護士です。
継続的な関係を結ぶことで、企業などの実情を踏まえた対応が可能になります。
ここでは、顧問弁護士の主な役割を紹介します。
日常的な法律問題についての相談
顧問弁護士の役割のひとつとして、日常的な法律問題への対応があげられます。
企業を経営していると、法律問題に遭遇するケースが少なくありません。
身近な法律問題としては、以下のようなものが挙げられます。
| 法律問題 | 具体的な相談内容 |
|---|---|
| 契約関係 | 契約書の作成、契約内容の確認、既存契約の見直しなど |
| 労務問題 | 就業規則の整備、時間外労働の管理、ハラスメントへの対応など |
| 消費者問題 | クレーマーへの対応 |
顧問弁護士の役割は、契約企業からの相談を受けて、これらの問題に対して適切なアドバイスをすることです。
専門的な知識がないと、各種トラブルにうまく対処できません。
対応が遅れてしまい、結果として状況が悪化することもあります。
顧問弁護士は、企業法務の「かかりつけ医」として、日常的な相談に応じる存在です。
有事でのスムーズな対応
訴訟や紛争などへの対応も顧問弁護士の役割です。
顧問弁護士がいると初動が早くなるため、事業に与える影響を小さくできる可能性があります。
速やかに対応できる理由は以下のとおりです。
【速やかに対応できる理由】
- 日常的な法律問題を相談している
- 企業の業務内容、取引先、社内規則などを把握している
- これまでの経緯を理解している
企業の内情やこれまでの経緯を把握しているため、訴訟や紛争が起きたときに聞き取りする内容を最小限にできます。
また、企業が重視しているポイントも理解しているため、より実情に即したアドバイスを提供できます。したがって、初動が早くなり、事業に与える影響を小さくできる可能性があるのです。
顧問弁護士と契約していない場合、トラブル発生後に弁護士を探して事情を説明する必要があるため、初動が遅れ、対応が後手に回る可能性があります。
社内規定の見直し
社内規定の見直しも、顧問弁護士が果たす役割のひとつです。
社内規定が古くなっていたり、実情に合っていなかったりすると、問題が起こりやすくなります。
たとえば、就業規則が労務実態に合っていないと、労使トラブルが起こりやすくなるでしょう。
具体的には、解雇した従業員から在籍期間中の賞与の支払いを求められるなどが考えられます。
顧問弁護士は、このようなトラブルを防ぐため、社内規定の見直しに関わります。
企業の担当者から聞き取りをして、実務に活用できる社内規定を目指す点がポイントです。
社内に明確なルールがあると、トラブルが起こりにくくなるため、会社経営は安定しやすくなります。
顧問弁護士は、企業経営における極めて重要な存在といえます。
法改正に関する対応
法改正への対応も顧問弁護士の役割です。
時代の流れとともに、さまざまな法改正が行われています。
近年注目された主な法改正は以下のとおりです。
【法改正の例】
- パワハラ防止法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)
- 個人情報の保護に関する法律
- 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保(働き方改革関連法によるパートタイム労働法・労働契約法・労働者派遣法の改正)
官報を確認すれば法改正に対応できますが、自社のスタッフだけで事業に関連するすべての法改正を確認することは難しいでしょう。
法改正を見落とすと、知らぬ間に法令違反となっている場合もあります。
知らなかったといっても、法令違反は免責されず、企業の責任が問われる可能性があります。
顧問弁護士は、専門性を活かして企業に関係する法改正の情報を提供してもらえます。
具体的な対応方法をアドバイスしてくれる点もポイントです。
顧問弁護士と契約していると、社会の変化にあわせて企業が柔軟に体制を整えやすくなります。
自社に適した顧問弁護士の選び方

続いて、顧問弁護士を選ぶ際に意識したいポイントを解説します。
自社のビジネスに関する知識を持っているか
自社のビジネスを十分に理解している弁護士を選任することが重要です。
業界ごとの特性を知らないと、法律的な知識があっても現実的なアドバイスを行えません。
また、専門用語がわからないため、ヒアリングもスムーズに行えないでしょう。
問題が起きたときに、速やかに対応できないことが考えられます。
したがって、契約前に自社のビジネス、業界に対する理解を確かめておくことが重要です。
同業種の企業と顧問契約を結んでいた弁護士、同業種のビジネス経験があれば、一定の理解があると判断できます。
企業法務に関する知識・経験は豊富か
企業法務に関する知識と経験を確かめておくことも欠かせません。
同じ弁護士であっても、得意分野は異なるためです。
弁護士の中には、交通事故や相続、離婚などを専門としている方もいます。
企業法務の知識や経験が不十分だと、実務に即した助言が難しくなります。
たとえば、リスクの高いトラブルを予想できなかったり、ビジネスにあわせたアドバイスを行えなかったりすることが考えられます。
ちなみに、企業法務は幅広い領域をカバーします。
【企業法務の例】
- 契約法務
- 労務法務
- コンプライアンス
- 知的財産
- 債権回収・債権管理
- 訴訟・紛争対応
これらの領域などに対応しなければならないため、専門的な知識と経験を求められるのです。
顧問弁護士を選ぶ際に、必ず事前に確認すべき重要な視点です。
レスポンスが速いか
素早く対応してくれる顧問弁護士を選ぶことも大切です。
会社経営におけるトラブルでは、法律のアドバイスを即座に必要とするケースが少なくありません。
具体的には、以下のケースなどが考えられます。
【早急な対応を必要とするケース】
- 顧客からクレームが寄せられたとき
- 契約交渉で法的な評価を必要とするとき
- 労務問題で早急な対応を求められるとき
顧問弁護士のレスポンスが遅いと、必要なときに適切なアドバイスを受けることができず、トラブルが拡大する恐れがあります。
したがって、契約前にレスポンスの早さや相談できる曜日と時間帯などを確認しておかなければなりません。
一定の期間内に返事を約束してくれる弁護士、休日対応してくれる弁護士であれば、急いでいるときでも安心できるでしょう。
相談しやすいか
相談しやすいことも顧問弁護士を選ぶポイントのひとつです。
気軽に相談できない関係性では「ちょっとしたこと」を相談できず、問題の種を見過ごしてしまう恐れがあります。
あるいは、気後れして基本的な事柄を質問できなかったり、センシティブな内容を話せなかったりすることも考えられます。
相談を先送りにすると、トラブルの対応が遅れ、顧問契約の本来のメリットを十分に得られなくなるおそれがあります。
顧問弁護士との相性は、契約前の面談などで確認できます。
十分な時間を確保して、丁寧に話を聞き、信頼関係を築ける弁護士を選定することが重要です。
依頼したい業務がサービスの提供範囲に入っているか
顧問弁護士によって、顧問料の範囲内で対応できる業務は異なります。
そのため、依頼したい業務がサービスに含まれているかを事前に確認することが重要です。提供範囲外のサービスを利用すると、原則として追加料金がかかります。
一般的には、顧問契約のサービス提供範囲は、契約書のチェック、簡易な契約書の作成、簡単な法律相談等です。
追加料金がかかる業務の例は、次のような個別案件です。
【追加料金がかかりやすい業務】
- 難易度の高い契約交渉
- 訴訟・紛争対応
- 債権回収、労働問題等の個別案件
追加費用がかかる案件を依頼するときには契約前に、その費用について明確に確認することが大切です。
関連記事:顧問弁護士にかかる費用相場は?依頼する業務内容別にチェック
顧問弁護士を選任するまでの流れ
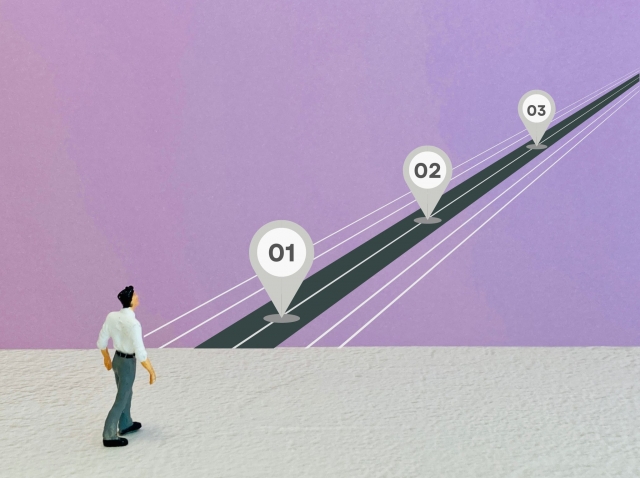
続いて、顧問弁護士選任までの基本的な流れを紹介します。
法律相談を申し込む
自社との相性を評価するため、気になる弁護士を探して法律相談を申込みます。
実際に話をしないと、自社にとっての相談のしやすさがわからないためです。
業界に対する理解、ヒアリングの質などを確認しましょう。
また、法律相談では以下の内容も説明しておく必要があります。
【説明しておきたいポイント】
- ビジネスの内容
- 顧問弁護士に期待していること
- 顧問料の予算
弁護士事務所の中には、初回の法律相談を無料で実施しているところがあります。
このような弁護士事務所であれば、気軽に法律相談を申し込むことができるでしょう。
関連記事:顧問弁護士契約の法律相談の範囲 | 青山東京法律事務所
複数の弁護士を比較する
1カ所の法律相談だけで、顧問弁護士を決めることはおすすめできません。
最初の弁護士が、最適な選択とは限らないため、比較検討が欠かせません。
複数の弁護士と面談を重ねて比較検討することが重要です。
基本的な比較ポイントは次のとおりです。
【比較ポイント】
- 自社のビジネスに対する理解
- コミュニケーションの取りやすさ(話しやすさ・専門用語の使い方など)
- レスポンス(返事のスピード、連絡できる時間帯など)
- 顧問弁護士としての経験
基本的には、この記事で紹介した観点をもとに、弁護士を比較するとよいでしょう。
契約を締結する
納得できる弁護士と顧問契約を締結します。
契約内容を明確にして、書面で確認することが大切です。
確認しておきたい基本的なポイントは次のとおりです。
【確認するべきポイント】
- 月額報酬
- 対応する業務の範囲
- 追加費用が発生する業務
- 契約期間
- 解約手続き
これらのほかに、気になる点がある場合は積極的に質問しましょう。
信頼関係を構築するため、疑問を残さず、十分に理解したうえで契約に臨むことが求められます。
顧問弁護士選びで失敗しないためには

残念ながら、顧問弁護士の選択で失敗したと感じることがあります。
ここでは、失敗を避けるため意識したいポイントを解説します。
依頼したい内容を明確にしておく
依頼したい内容を明確にすることが、顧問弁護士を選定する際の出発点になります。
それが曖昧だと、顧問弁護士に求めるスキルがわかりません。
労働問題の相談が主になるにもかかわらず、契約書のチェック、作成がメインで労働問題についての経験の浅い弁護士に依頼してしまうこともあります。
また、訴訟対応が中心なのに、相談がメインで訴訟経験の少ない弁護士に頼んでしまったという場合もあります。
自社に適した顧問弁護士を選任するため、まずは「何をしたいか」を明確にすることが大切です。
関連記事:契約書の作成は弁護士に依頼するのがおすすめ!メリットや費用は?
面談を複数回実施する
失敗を避けたい場合は、面談を複数回実施してから顧問弁護士を選びましょう。
複数回の面談によって、弁護士の人柄や姿勢をより深く把握できます。
具体的には、以下の点などを理解できる可能性があります。
【複数回の面談でわかること】
- レスポンスにかかる実際の時間
- アドバイスの質、わかりやすさ
- 弁護士の得意分野
- 自社との相性
単発で業務を依頼して、対応を見てから顧問契約を締結することもできます。
慎重に対応することで、選任ミスの可能性を低減できます。
顧問料が相場と比べて高額すぎないか確認する
一般的な月額顧問料の平均額は5万円~10万円程度です。
弁護士にとっては、対応にかかる時間が大切ですので、5万円の契約ですと、大体2時間程度の時間を割いてもらえます。もっと多くの時間を使って対応してもらいたい場合には、10万円のプランを利用することも考えましょう。
ただし、弁護士に頼む時に、平均の金額というものにあまり意味はありません。
どの業界でも同様に、優秀な弁護士や将来にわたって的確なアドバイスを提供できる弁護士には、それ相応の報酬が必要になることがあります。
選び方にこだわって企業の成長を支える顧問弁護士を見つけましょう
ここでは、顧問弁護士の役割および適切な選定方法について述べました。
顧問弁護士の主な役割は、日常的な法律問題の相談に応じることや事業に関連する法改正に対応することなどですが、何よりも大切なのは、信頼できる顧問弁護士、頼りになる顧問弁護士を見つけることです。
東京の顧問弁護士なら青山東京法律事務所は、顧問弁護士として深い経験を有していますので、他の事務所とはひと味違った質の高いサービスを提供できると自負しています。
顧問弁護士をお探しの方は、ぜひ青山東京法律事務所にご相談ください。
監修者

植田 統 弁護士(第一東京弁護士会)
東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士
東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。
野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。
米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。
2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。